



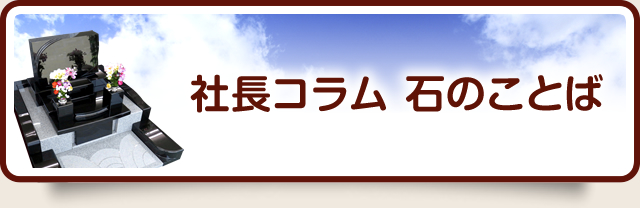
HOME > 社長コラム 石のことば
エーゲ海にはたくさんの島がありますが、それぞれ特徴もあって、観光客にも人気の島がいくつかあります。
その中でも常に人気1位2位を争う島がサントリーニ島です。
現地では別名で表記されることもあり、ティーラ島(島の中心地フィラからそう呼ばれるそうです)とも言い、地図や飛行機の宛先でちょっと勘違いすることもあって統一してくれるといいのですが、まずますサントリーニ島で通じます。
この島が有名なのはやはり島の形、建物の密集状況、建物の色の統一性、そして夕陽でしょうか。
島の形とは、サントリーニ島とはいくつかの島が総称なのですが、その島々で円形を作っています。円の中心には火山の噴火口のある島があり、円形のうち所々が海の中に沈み、三日月形や勾玉型の陸部分が島として残っており、大陸が海の中に沈んでしまったという昔のアトランティス伝説のモデルになった場所と言われています。
一番イメージしやすいのは火山の噴火口の回りにカルデラ湖として水の下と山の稜線に分かれた形が、海の中に出現してると思うと形がわかると思います。
島の中には紀元前時代の高度な文明を匂わせる遺跡も発見されているそうですので、まるで日本で邪馬台国の論争と同じようにアトランティスのロマンがあふれているのでしょう。
建物の密集状況は写真にあるように、噴火で崩れ落ちた崖上のわずかな高台に街が密集して家を建てていることです。実はこの島にはもっと平地もあり、農地やブドウ園もあります。現地の人に聞くと、観光が盛んになる4,50年前までは、この高台の土地は安く、島の住民の次男三男で家の農地を相続できない人たちが仕事を求めて街に住み着いた。長男は広い農地と低地に家をもらって農業を続けた。でも今はその長男たちの農業はそれほど変わらないが、次男三男の高台地は観光産業や高級ホテルが建ち並び一気に土地が高騰したそうです。
産業構造と土地の価値、世界中どこでも同じ話ですね。
そして色はもちろん、青と白の統一です。
エーゲ海の海の青、そして教会の青のドーム、建物は基本的に白、時に淡いピンク、単純な色使いでもそれが街全体、島全体に統一されると圧倒的な美しさです。
また、サントリーニ島は沈む夕陽が最も美しい場所と言われ、日本の初日の出詣りのように、毎日夕陽詣でで多くの人々が夕陽ポイントで大渋滞します。でも、確かにエーゲ海にゆっくり沈んでいく夕陽は時を忘れ、自然と一体となったような体験でした。
最後に、サントリーニ島の石について。
噴火で火山灰や火山礫が飛んできたでしょうから、海岸や農地には黒い火山岩が多いです。
農地の開墾には大変な思いをしていると思いますが、そのせいもありブドウは良く育つようです。そうなるとワインもよく出来ます。小さなサントリーニ島ですが、いくつかのワイナリーやワイン博物館もあり、島のワインの歴史の勉強とともに、ワインの試飲は、あえて記載しなくてもご想像のとおりです。
アテネからミケーネに行く途中に、ちょうどペロポネソス半島の一番くびれたあたりにコリントスという街があります。
実は知っているようでみんな知らない常識なのですが、このペロポネソス半島というのはほんのわずかな人口海峡を挟んで島になっているのです。
これは19世紀にスエズ運河を開削した人が二匹目のどじょうを狙ってここに運河を作って分断したためです。
写真1でわかるように川幅こそわずかに23メートルしかないものの、崖の高さは最大79メートル、長さは何と6.3キロメートルのコリントス運河によって完全にギリシャ本土とペロポネソス半島(島)を分断しているのです。
時間とお金をかけて完成したものの、スエズ運河ほどにはその利便性や認知度は無いのですが、近年はこの運河を船で渡る観光船が活躍しているようです。
そんなコリントスですが、ミケーネ時代はペロポネソス半島のスパルタやコンリトスとアテネなどの本土を結ぶ中間地点として、流通や貿易、また海運などで大いに栄えた時期があったようです。
写真2は古代コリントスのアポロン神殿で今は近くに博物館が併設されており、街に隣接する急峻な岩山の頂上には街の守り神であるアフロディーテ(ビーナス)の神殿もあります。
紀元前は如何に繁栄していたのか、その石組みの城壁や発掘再現される建物の立派さは容易に当時を思い起こせます。
そしてもう一つ、中学高校時代の聖書の時間(中学高校はミッションスクールで週1回の聖書の時間がありました)で覚えさせられた、キリストの弟子パウロによるコリント人への手紙というものが、ここコリントスが舞台であったことをここで初めて知りました。
使徒パウロはキリストが処刑された後、その教えを広めるためコリントスに滞在し、信者を集めたものの、後にコリント市民が堕落するのを聞いて、それを諭したのがコリント人への手紙1、2ということだったそうです。
そして写真3がパウロがコリントスに滞在しているときにコリント人に教えを授けた広場と言われています。
2000年前の息吹がすぐそこにあるような、タイムマシーンのような石組みの街でした。
すごく古い話で恐縮なのですが、中学校2年生の時に、夏休みの読書感想文の為に読んだのがハインリッヒ・シュリーマンの「古代への情熱」でした。
トロイの木馬 で有名なトロイ(トロイア)の場所を特定し遺跡を発掘したことで有名です。
まだまだ向学心に燃える当時の中学生にとって、ホメロスの叙事詩イリアスを信じて(当時はまるで神話のように架空の話と思っていたとシュリーマンは主張しています)実際にその場所を特定しました。
また、遺跡発掘の資金源を作るために実業家として財を成し、41歳でその事業の収益でその後次々と歴史に残る発見をしたり、二階の屋根裏部屋にこもって各国の言語をそれぞれ6か月程度で習得し、最終的には18か国語を話せたという逸話などを読み、純粋に感動したものでした。
後の余談ですが、大人の世界ではシュリーマンはあまり評価がよろしくなく、武器商売で財産を築いたとか、トロイの発掘ではダイナマイトで地層を破壊し、考古学的には後の検証を不能にした単なる墓荒らしだとか、18か国語の話も誇大妄想癖であるとか、一面では散々な評価もあるようです。
ただ、そのシュリーマンにも確実な成果もあり、二つ目の有名で偉大な発見が、ギリシャ西部のミケーネ遺跡の発見です。
世に言うアガメムノン王の治めた地であり、当時のギリシャきっての強国です。
そのトロイ戦争ではギリシャ連合軍の総大将を務めたアガメムノンの王国です。
こちらも長い間、その存在は信じられていても場所が特定できず、たくさんの人がその発見を競っていたようです。
シュリーマンも何度か別なところを掘って、失敗も多くしたようですが、最終的にはペロポネソス半島内の中ほど、田園地区の小さな丘が並ぶうちの両側が崖で守られ、後ろが細い尾根で奥の山脈に続いている一つの丘陵に眼を付け、そこを掘ったところアガメムノン王のマスクと言われる黄金や宝石が王家の墓とともに発見されました。
そこはまさに攻めるには難しく、守るにはたやすい好立地であり、また当時の主要な産業である農産物生産の中心地、貴金属や鉄なども取れた場所なのでしょう。
昔の一大中心地であったことが垣間見られます。
王域の周りは巨大な石垣で囲われており、その入り口となるのが獅子門と言われる、いまだに天井石が3メートルの枠石の上にどうやって載せたか謎の三方が石で出来た門です。もっとも床も石で出来ていますから四方が石で出来ている中を通り過ぎてその中に入るのは当時としては驚きだったと思います。
王家の墓は三重の柵でまわっていて、遺骨を囲んだ小さめの柵の周りに、日本の古墳ほどもある大きな外の柵が二重に、まるで外溝のように石が並べられてありました。
二番目の柵の中は、その上に土をかぶせて埋めてしまうのも何か日本の古墳に似ているように思います。
説明ではその外周の回りを警護の兵士が四六時中警備していたという話です。
土で埋めた上には割と小さな石の墓標があったらしく、最後の写真は別な場所にある王の家族の墓の実際の墓標です。
紀元前1500年或いは紀元前1300年代の話で、今から3500年前のお墓の中と、墓標とよくもまあ残っているものです。
いつも思いますが、これが金属や有機物では今に伝えることができないですが、石だからこそ その古代のロマンが伝わり 古代への情熱となっていくのでしょう。
ギリシャきっての繁栄を極めたミケーネもアガメムノン王の死後、中継貿易で栄えたコリントスに覇権を奪われ、そしてさらには都市国家のアテネに移ろい、いつしか忘れ去られてシュリーマンが見つけるまでの長い年月、静かに眠っていたのでしょうか。
次には34年前にはもっと考えられなかった、ギリシャの一般人のお墓、霊園への訪問です。
近代オリンピックスタジアムから程近く、パルテノン神殿のあるアクロポリスの丘も見えるアテネの一画に市営の霊園があり、公務員らしき管理人さんに挨拶して中に入りました。
ギリシャのほとんどの埋葬法は土葬で、それなりの場所が必要ですが、その霊園に入ってすぐの一番いい場所は歴代の首相や政治家、大実業家などがその土地を所有(購入)して埋葬、その上に名前や業績、場合によってはその人の石像を飾って、全体を白大理石(おそらくペンテリコン系統)で作ってあります。
さすがにこれだと、墓地事情がかなり窮屈になって、いずれ市内の墓所はいっぱいになるだろうと思われましたが、詳しく聞くと墓地の使用には大きく二通りあって、一つは土地購入による所有(日本でいう永代使用か)ともう一つはレンタル(賃貸使用)があるとのこと。
そのレンタルについて興味があり現地の人にさらに詳しく聞くと、政治家や富豪など稀には墓地を所有して同じ場所で埋葬お参りするが、一般庶民は墓地を永代で所有せずに3年間のレンタルで埋葬し、3年後に掘り出して集め、洗骨して入れ物を別にして壁墓地や一族の集合墓に入れるとのこと。
つまり、火葬しない代わりにそのレンタル埋葬地がお骨の製造地であって、その後にきちんと行き先があり、その場所はまた別の人に貸し出されるという流れのようです。
ギリシャ国内にも霊園事業者というのがいて墓地購入も、レンタルもそれなりの金額のようですが、公営霊園の場合は一人当たりのお棺が埋められる面積の3年間のレンタル使用料は350ユーロ、日本円で5万円弱です。
かなりリーズナブルで、かつ土地利用の観点からすれば合理的と言えると思います。
ただ、合理性だけでは考えられないのが、さすがに石の国だからか、わずか3年の仮墓石であっても、その石碑はたいそう立派であり、かつ故人を偲ぶ、供養する気持ちからか、永久の所有墓石なのか3年の限定墓石なのかわからないくらい、きちんとした石のお墓を建てていることです。
おそらく3年間が日本でいう三回忌や七回忌、或いは十三回忌のような役割で、その間は絶えずお参りし目印となる石碑にも凝って作るのではないか。
その後は集合墓に安眠してもらうという考え方があるような思いを受けました。
まさに、その日もたくさんのお参り客とすれ違い、花を手向ける姿を見続けました。
34年前には考えられない霊園見学を終えて出口に戻ったら、手足のいたるところが赤く腫れて痒くて、、、、
入口ガードの公務員守衛さんが、今年は蚊が特に多いんだと言っていましたが、それなら先に言ってよ、やっぱりギリシャの公務員は仕事しないなとあきれながら、かゆみ止めを買いに薬屋探しも、昔と違う行動パターンとなりました。
今から34年前、初めてヨーロッパに行ったのが実はギリシャでした。
アテネ、ミケーネ、エーゲ海のクルーズなど、当時はワインもオリーブもそんなに得意でなく、食事や気候に苦労したことを覚えています。
その後、大理石の仕事でイタリアやスペイン、ポルトガル等 ギリシャと気候、風土の似ている国々に何度も行くようになり、ヨーロッパはかなり身近に感じていましたし、またギリシャ産の白大理石も年に数度の割合で購入していたりしたので、もっとギリシャに行っていたように勘違いしていましたが、何と今回の訪問が実に34年振りとは、我ながらビックリでした。
アテネでは当然ながらアクロポリス、そしてパルテノン神殿、確か34年前にも工事中だったように記憶していますが、今回もクレーンと足場がかかっており、まあパルテノンはいつも工事中という評判通りの風景でした。
でも34年前と違ったのは、当時は石屋になる直前、つまり石には興味はあったものの、その石の材質や工法、歴史としてとらえる視点はあっても、専門家としての視点はまだ未熟だった私の経験の差です。
パルテノン神殿に使われた石の多くはペンテリコンという白に薄いグレーの模様のあるギリシャ産の大理石、一部にはギリシャ北方の薄茶の大理石や緑系大理石、またエーゲ海で採れるライムストーン(石灰岩)等も見受けられましたがきわめて僅かです。現状は薄いベージュ系の色に見えますが、空気や水分、酸性雨などの影響によるもので、中味は完全な乳白色です。
また、女神を模した柱の彫刻も、女神像を作ってから柱にしたのではなく、柱として設置した石からのちに女神像を彫り出したもので、頭部は割と詳細に作ってありますが、体や脚部は柱の一部として割りと簡易的な彫りとなっているように見えます。
尚、パルテノン本体の柱には世界史で習ったドーリア式やイオニア式などありますが、それ以上に専門家の目から見ると柱は一本の石でなく、何個も横に重ねて繋いであって、またそれぞれの石の中には「ほぞ」と言われる凹部、凸部で繋いでいたり、一部は金属のくさびを打ち込んであったりと、さすが2500年も残った工法だと感心しました。
また柱の縦の模様も女神像同様に、先に石を重ねて繋いでから、模様を現地で彫っていったものと見受けられ、模様のラインがきれいに縦に揃っています。
石屋になって34年経つと当時気づかなかったこと、関心の範囲でなかったことなど、あらためて自分の変化とともに、対照的に以前と変わらずそこにあるパルテノンの石の不変が妙に思い描かれました。
石は変わらず、それを見る個人や人が変わっていく、まさに歴史を伝える石の役割です。
ホテルの格付けに5つ星ホテル、4つ星ホテルなど星の数でランキングしているのは知っていましたが、初めて7つ星ホテルという格付けを見ました。
何を隠そうドバイのジュメイラ地区のプライベートアイランドにある「ブルジュ アル アラブ」というホテルです。
1999年にアラビア船(ダウ船)の帆をコンセプトとして高さ328メートルのホテルを人工島の中に完成しました。
建物としては中心柱の無い吹き抜け仕様、デザインや中の色彩は金色や紅色を使った豪華絢爛なつくり、202室の客室は全てメゾネット(2階建て)のスイートルーム、一泊最低一人15万円からというとんでもないホテルです。
フロア各階には階毎にコンシェルジュが居て、お客様の要望に応え、また室内のアメニティは全てエルメスの提供だとか・・・・
豪華すぎてとてもでないけどビビってしまいます。
でもせっかくドバイに行ったので見てみたいと画策したのですが、ホテルのはるか手前の人工島の入口にセキュリティチェックがあり、宿泊者や関係者以外はホテルの近くにも行けない状況です。
それでも何か方法が無いかと聞きまわったところ、アフタヌーンティーを予約すればホテルロビーとフロントレストランには入れるとの事。
予約が混んでて厳しいかもというので急いで現地で予約を入れてもらったら、何とか1席だけOKという事で早速現地へ。
確かに中はびっくりするようなデザイン、色彩、雰囲気です。(あまり落ち着く感じはしませんが…)
そして宿泊者と思しき人の多くが中国人?又はインド人?で、ヨーロッパ系では一部ロシア系?の人が居るくらいで、やはり落ち着きません。日本人では噂によると神田うのが定宿にしていたと言われています。
石材はブルーパールを多く使用し、豪華さ高額さ差別感といったものを前面に押し出しています。
まあ確かに豪華絢爛ではありますが……
また、ホテル格付けに7つ星というのは本当は無くて、いわゆる自称という事だと後で聞きました。
最後に会計したらアフタヌーンティーの代金は一人18,000円!!!
(日本なら2食付で温泉宿に泊まれますね)
いろんな意味でのビックリでした。
アラブ首長国連邦の首都はドバイではなく、アブダビです。
アブダビもいろいろな世界一や観光名所がありますが、近年特に観光客が多いのは、アブダビのイスラム教寺院、「ジェイク・ザイード・グランド・モスク」です。
イスラム教ではなかなか他宗教の人がモスクに入る事は難しく、柔軟な考え方をしているUAEの中でも、我われが入れるモスクはドバイも含め非常に少ないです。
ところがこのジェイク・ザイード・グランド・モスクは観光客でも入れますが、そこはやはり荘厳な宗教施設なのでいろいろと規制は厳しいです。
特に服装や、中での飲食、立ち入り禁止区域など常に警備員が目を見張らせています。
例によって中国の団体さんが何度も注意を受けており、その近くにいるとこちらもとばっちりを受けそうになり大変残念な思いもしました。
さて、その非常識観光客は別として、このモスクを見た瞬間にその巨大さ、その美しさ、その素晴らしさに唖然として声も出ない状況です。
私には凄まじいばかりの大きさで、これも世界一なのだろうと勝手に想像していたら、何とモスクの中ではこれで世界6番目との事。世界はどうなっているのか改めてビックリしました。
ただここのペルシャ絨毯は紛れもなく世界一で手織りで一枚織りだそうで金額で9億円と言われています。
また、ここのスワロフスキーのシャンデリアも1個で7億円でこちらも世界最大とか。
でも私が本当にびっくりしたのは、まぎれもなくここの大理石です。
金額はどこにも資料として残っていませんが、イタリア側の石材業者の話では白大理石の一つの採掘エリアを3年間借り切ってその中でも良質の石だけを提供させた、と言われています。
イタリアの白大理石ビアンコ・カッラーラの採掘エリアはカナルグランデやロラーノ等の著名な採掘エリアがある中、その貸し切りにした丁場の石はその後数年間全く市場から姿を消して、良質の物だけがアブダビでモスクとなって再び現れたのです。
床のモザイクも、壁や柱の加工技術もまさに石屋として見たら、目の保養であり驚愕の出来栄えです。
金額を言っては失礼かもしれませんが、過去の石工事の経験から100億円では無理と思います。
その2倍、いや3倍以上の金額の石材がここに費やされていると思います。
当社でその100分の1でもこの仕事がしたかったなあと、モスクを見ながら思っていました。
ドバイと言えば建築物の素晴らしさ、特異さ、そして何でも世界一で有名です。
今更ながらですが、一応ドバイの基礎知識としては、ここはもはや産油国ではありません。
観光立国、ビジネス立国で、石油への依存は10%も無いと言われています。
元々ドバイは国ではなく、首長・族長の治める王国です。その王国が7つ集まってUAE(アラブ首長国連邦)として国際社会では認識されています。
最も大きい首長国はアブダビ、ここは石油が豊富でドバイのそれと比べると石油依存は70%とも80%とも言われています。
UAEの大統領は常にアブダビの王様が、副大統領はドバイの王様が継いでいますから、7つのうちの2番目に大きく豊かな王国と思います。
このドバイがそこまで有名になるのは、実は初代の族長シェーク ラシッド王のおかげと言われています。
「限りある資源(石油)に頼る国家経営は良くない、脱石油で世界一を目指す」
という方針のもと、世界中から優秀な人が来るように、紛争や宗教で争いが起きないように、そして観光や石油以外のビジネスで豊かになるように、政治を引っ張っていた先駆けです。
今の王様(UAEの副大統領)はその息子のムハンマド ラシッド、皇太子は3代目の美形のハムダン ラシッドでいずれも経営能力の図抜けた王族です。
最も有名な現在世界一の高さ(828m)のバージュカリファ(ブルジュハリファとも言う)はトムクルーズが実際に登って撮影したところです。
室内装飾も円形アーチをふんだんに(これ以上ないという位のしつこさで)続いていますし、昔のアラビア風の家屋との棲み分けも十分考慮して、どんどん世界一を作って、人も物も金も情報も、ドバイに集まるようにしているすごさを感じた次第です。
人は死んだらどうなるのか、来世や浄土・極楽・天国はあるのか、それは個人の死生観だけでなく宗教観によるところがかなり大きいと感じます。
昨年、ドバイやアブダビなど7つの首長国連合からなるUAE(アラブ首長国連邦)に行ってきました。
当然ながらイスラム教の世界です。イスラムの死生観はある意味キリスト教に通じるものもあり、救世主がこの世に現れその瞬間にすべての人類(故人も生きている人も)が裁かれて、天国か地獄かの判決を言い渡されるのでその時に肉体が無いといけない、つまりは遺体は絶対に残っていなければならない。日本のように火葬率がほぼ100%の民族は、イスラム社会にとっては信じられない、死後の行き場を失っていると思われるのかもしれません。イスラム社会はほぼ100%土葬のようです。
キリスト教でもある意味同じように死後の復活を信じて火葬をしない傾向が高いですが、一部のキリスト教社会ではすでに50%近くまで火葬率が上がっている国もあるようですので、それと比べるとイスラム社会はかなり厳格に火葬を拒否しているようです。
そこには国の土地の広さや砂漠化など、イスラム教が多いエリアには広大な乾燥した砂漠地帯があり、土葬に適した?国柄であるからか、国土が狭く死者がゆっくり眠る土地を与えられなくてしょうがなく焼骨で埋葬するのかなど他の理由もあるのでしょうが、ところ変われば…です。
さて今回、ドバイで墓所を案内してもらおうと思ったら…、墓地は全て政府の直轄エリアで、すべて高い塀に囲まれており(写真 )一般人、ましてや観光者が立ち寄ることもできなければ、車を近くに止めてもすぐ脇にある政府直轄の警察組織が不審者として引っ張っていく雰囲気(本当にそうかはわかりませんが)で、遠慮がちに望遠レンズで中の墓地を撮影しました。(写真 )
一部の人は土葬で埋葬して1年、3年、5年程度までは一応目印になるような簡易お墓や石の目印を置いておくようですが、基本はエリア(敷地を示す日本でいう外柵)のみ示してあって中は本当に土のまま、砂利のまま、草の生えるままのようです。写真 は今回のドバイの例でなく同じイスラムのサウジアラビアの墓地の例です。
このように土葬の場所がいずれ分からなく可能性もあるのですが、ドバイの風習ではたとえ奥さん、娘でも女性は遺体埋葬に立ち会えず、その後も墓地にはなかなか行けないので、夫や親がどこに埋葬されているのかわからないケースも多いと聞きました。
なかなかわれわれの供養感や死生観では理解が難しいのかもしれないですね。
ナポリの最後はやはり青の洞窟の事を書かないといけないかと思います。
実際にはナポリから高速船で約1時間(結構揺れて船酔いの酷い人には厳しい)でカプリ島に着き、そこからモーターボートで島を巡って、洞窟の前では海の上でボートから手漕ぎ舟へと乗り換えての結構な行程があります。
この前日まではかなり風も強く、波が高かったせいで3日連続で青の洞窟には入れなかったそうで、年間平均で3日に1日くらいしか洞窟には行けないと聞いていたのですが、3日連続駄目なら次は大丈夫だろうという安易な考えで、まあ今日は大丈夫かなくらいの思いを抱いて、ナポリからカプリ島に向かいました。
波の程度がどの位で決行、どうだと中止かわからないので着いた時に確認するのですが、ガイドさんがしばらく問い合わせに行っている間、大きな看板を見ながら(写真 )青の洞窟を思い描いていたのですが……
何とこの日も今の時点の判断で本日の欠航が決まり、高速船で来た観光客は全員急遽カプリ島観光に変更。
バスやロープウェイでカプリ島の頂上に登ったり、島内のお土産屋や観光スポットを回ることになりました。
残念だったのは確かですが、でも島内を回っている間に島の墓地があって、仕事柄ちょっとガイドさんに断わって整備の行き届いた霊園内に入りました。(写真 )そこには綺麗な花を手向けた普通の墓石とともに壁墓地もあり、小さな島の狭い墓地の有効活用を見ることが出来ました。
また、青の洞窟訪問だと、ほとんどが海の上での時間となり、ナポリに戻ることを考えたらカプリ島ではほんの短い時間しか無く、かなりの駆け足での観光となるそうで、本当の青を見ることが出来なかったのは残念ではあるものの、島の周りも全て綺麗な青の海が広がり(写真 )、(洞窟内の青はレベルが違うとの事でしたが)きれいな空気とゆったりした島の散策で、これも致し方なしとあきらめて戻りました。
最終日にもう一度小舟が出せたかどうか聞くと、その次の日も、そしてその次の最終日も欠航で連続6日間の中止だったそうです。
統計からするとその後に行った人はかなりの高確率で見れたんでしょうね。
うらやましいです。
絵葉書を買ってこちらは我慢しました。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.