



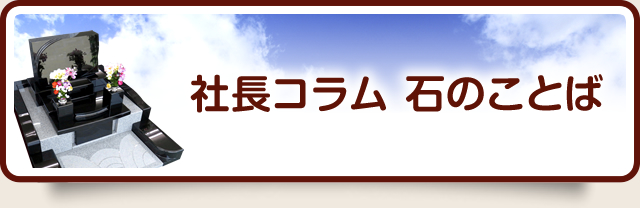
HOME > 社長コラム 石のことば
いよいよ2020(2021?)東京オリンピックが開催されました。
ここまで来るには主催団体も開催都市も開催国も、医療問題、政治問題、時間的経緯、主義主張の違いなど、まさに二転三転し国民も全世界も翻弄され続けました。
でも一番大変だったのはオリンピックに参加する選手たちだったと思います。
自分の夢、世界中が見つめる大舞台に出たい気持ちと、コロナ拡大危機の中での葛藤。
オリンピックは出れる事が選ばれた証であり、参加することに意義があるとよく言われてきました。
目標は皆、入賞だったりメダルだったり、勿論誰もが金色の最高峰を目指しているとは思いますが、このコロナの特別なオリンピックに参加した事ですべての参加者に敬意を払いたいと思います。
さて、今回はオリンピックの話ではなくて、かつてオリンピックと同じように「参加することに意義がある、オリンピックのような石屋の現場」があったことを紹介します。
時はバブルの真っ盛り1990年(平成2年)完了の超巨大ビルにかかる石工事の現場です。
もちろん誰もが知っている新宿の東京都庁です。(写真は上の中央が第一庁舎、二番目が第二庁舎、最後が渡り廊下です)
外壁は総石張り、石材の施工面積は第一庁舎外壁が約57,000平方メートル、第二庁舎外壁が45,000平方メートル、渡り廊下部分が8,000平方メートル、3カ所合わせて外壁の総面積110,000平方メートルは空前絶後の数量です。
もちろん内部の床や壁にも石材が多数使用されており、その数量24,000平方メートル、内外合わせると石は134,000㎡も使われています。
これは、当時の石材店1社が年間で製造も施工も2,000㎡とか3,000㎡とかが平均値であり、大手といえども10,000㎡はかなり重荷だった頃の話です。
しかも建築の工期は1988年4月~1990年9月迄の2年半、石工事は建築工程の後半なので最後の1年間でこの膨大な量の供給が必要だったので、初めに書いた「とにかく石屋として参加することに意義がある」のような形で日本中の石屋がこの現場に関係しました。
当社も、当時は未だそれほど都内の物件に入り込むことは少なかったのですが、外壁の(ほんの)一部ですが、工場加工と施工協力を行いました。
当社の分は確か2,000㎡位だったかと思いますが、全石材量からすると1.5%にしかならないのに、当社にとっては大変な量を非常に短期間で対応させていただきました。
日本中の石屋が一つの物件に集まり、まるでオリンピックのような注目度の中、参加できた事に誇りをもって取り組んでいました。
のちのち、石屋の世界では、「お宅も都庁(の現場)に入ったの?」「下請けの下請けでうちも都庁やりましたわ」などまさに日本中、いやイタリアの石屋、採掘現地の石屋など世界中を巻き込んで、オリンピック同様の狂騒の時期でした。
ちなみに外壁の8割がたはスペイン産のホワイトパールという御影石です。色の淡いグレーの方です。残りはスエーデン産のロイヤルマホガニーという褐色の濃い方の石です。
内部の床はイタリア産のローザギャンドーネ、ほんのり薄いローズ色のグレー御影です。
内部壁には日本人が最も好む白大理石、ビアンコカララが多数使われています。
バブル真っ最中の建物で、使用石材も当時は世界最多を誇りました。
東京オリンピックの開会式を見ながら、30年前の石屋のオリンピックと言われた、東京都庁の石に思いを馳せ、あの狂騒の時を懐かしく思い出していました。
石の人物像を現地で見て、想像していた範囲を超えて強烈に印象に残っているものがいくつかあります。
今回は石(大理石)像の中で特に衝撃を受けたものを紹介します。
先ずはフィレンツェで見たミケランジェロのダビデ像。
美術や西洋史の教科書にも載っている超有名な像ですので写真では何度か目にしていましたが、本物を見た印象は「なんて巨大な!」でした。
一つの石の塊りから掘り出されたダビデ像は何と高さが5メートル17センチメートル、普通の男性の3倍の大きさです。重さは5.66トン、人間の体重と比べると70人~80人分です。
これを当時26歳のミケランジェロが3年ほどで作り上げたということで、その熱情と共に力強さを感じます。
このダビデ像は石の堅固さと巨大さを前面に出して作られた1504年から、現在に至るまでフィレンツェのシンボルとしてそびえ続けています。
次はパリのルーブル美術館で見たサモトラケのニケ像です。
こちらはエーゲ海のサモトラキ島で1863年に見つかった古代の遺跡です。
ニケ像だけで2メートル44センチメートルですから、こちらも大きな像ですが、この像の下は台座代わりに土台と石の船もあり、そちらと合わせると5メートル57センチメートルとダビデ像に匹敵する巨大さです。もちろんニケ像と台座の石は別物なので、よく一緒に見つかったなと感心します。
こちらは紀元前190年というから作者は当然わかりませんが、着ている服の襞まできれいに再現されているのは、ルネッサンス期の彫刻作家にも負けない作りです。
そして、服の襞の再現、布の柔らかさを硬い石で表現しているものといったら、ダビデ像と同じ作家ミケランジェロのピエタ像です。
バチカンのサン・ピエトロのピエタと言われています。
ミケランジェロにはピエタの作品が4つあり、そのうちバチカンにあるこのサン・ピエトロのピエタは特に評価が高く「The ピエタ」と呼ばれ他のピエタを代表する傑作と言われています。ミケランジェロの初期作品でありダビデ像に取り掛かる前の1500年には完成していたといわれています。
この像を見た時、大きさはそんな大きくはなく(174センチメートル×195センチメートルで等身大かそれより若干小さく見えました)目に迫るものではないのですが、その洗練さと柔らかさが心にしみてくる石像でした。
マリアやキリストが身に着けた衣服の襞や肉体の表現が石を超えた何か神秘的なもので作られたような、まさに心に響く作品でした。
しばらくここを離れられなかった思い出があります。
最後に一つだけ上記の3点に負けず劣らず印象に残っているものも紹介させていただきます。
サン・ピエトロのピエタの衣服の柔らかさと同様、男性の筋肉、女性の柔肌を同じ大理石で表現したローマ、ボルゲーゼ美術館のプロセルピナの略奪という彫刻です。
こちらはイタリアのベルニーニが1622年に作ったものです。
大きさは2メートル25センチメートル、等身大よりは1.5倍ほど大きいですが、皮膚や筋肉の動きを大理石の中に瞬間で固めたみたいな見事な作品です。
これも、展示品の前からしばらく動けなかったほどの衝撃でした。
(構成の都合上写真は3点までのため、プロセルピナの略奪は載せられませんでした。ご興味があればご覧になってください。)
洋の東西を問わず石像はいくらもありますが、なぜか複数で縁起のいい数をまとめて一つのセットにしていることがあります。
例えば日本では七福神というものがあり、こちらは特に石像にしているものを多く見ます。
七福神をすべて諳んじられる人は余程の物識りでしょうから一般的にはその来歴やそれぞれの由来などあまり知られていないことが多いと思います。
一応確認すると恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋となっていますが、よくよく調べるとこの中には重複している神様もいたり、他の神を入れて八福神と言うくくりもあったり、地域によって違ったりとあまり統一されていないようです。
それもそのはずで、この七福神はもともと一つの由来や縁起話で出来た話でなく、仏教や、儒教、道教、インドのバラモン教や民間風俗などいろいろな宗派?の神様を縁起の良い七の数でまとめたもののようです。
それであればバラバラの神様ですが、お正月の宝船に一緒に乗り込んでいたら何か同じ仲間に見えてくるから不思議です。
西洋でも教会では建物自体に聖人と呼ばれる石像がたくさん上がっています。
キリスト教に貢献した高名な信者や使徒たちの実在の像なのでしょうが、こちらもキリスト教内の宗派や地域によってその聖人がたくさん居て我々にはどの人がどの像なのか判別が難しいところです。
聖書や最後の晩餐で有名な12使徒くらいはかろうじて分かるかもしれませんが、全ての名前を出すにはやはり調べないと‥‥
12使徒とはペトロ・アンデレ・大ヤコブ・ヨハネ・フィリポ・バルトロマイ・トマス・マタイ・小ヤコブ・タダイ・シモン・イスカリオテのユダ・マティアだそうです。
あれ?
13人居ますね。
もっと調べると、もともとはイスカリオテのユダまでが12使徒だったのですが、キリストを裏切ったユダを12使徒から除いてマティアを繰り上げて12人の中に入れたとあります。
こちらもなんか13という数字にしたくなくて12にこだわったような気もしますね。
さて石像には数をまとめてセットにすることを書いてきましたが、よくよく考えると中国の秦の時代にはその数が、半端ない桁になっているのがありました。
兵馬俑の兵士の像です。
その数8000体と言われています。
縁起がいいも悪いもない圧倒的な数の力ですね。
まあ、残念ながらこれは石造ではなく陶製ですが、その硬さや永遠性は石にも劣らない歴史の遺産であると言えますね。
前回のコラムで趣味は石かもしれないと記載したら、知人からこんな石もあるし、こんなのは何?と質問のような又確認のような連絡がありました。
質問の一つは河原の石って材質は何なの?というものでした。
誰もが小学校の理科で丸い石は川を下って来る時に角が取れで丸くなっているので、川の上流の石は四角くても下流になると丸い石が多いことや、漬物の石にちょうど良い形のものがあるとか河原の石にはそれぞれ愛着やイメージがあることと思います。
実はあの河原の石は何と様々な種類の石のサンプルなのです。
写真2にその特徴的なものとしていくつかの種類が写っていますが、これらの小石は全て出来た場所も川を下ってきた源も石の中の素材も全く違うものです。
そもそも火山岩系、堆積岩系、変成岩系という大どころの違いから始まり、火山岩系では流紋岩、安山岩、玄武岩があり、同じ火山岩の中の深成岩系では花崗岩、閃緑岩、斑レイ岩とあり、また堆積岩系の泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩などや、変成岩系の大理石、結晶片岩などと専門家でも迷う実に多くの種類がありますが、この河原の石にはその多くが含まれていることから石のサンプルの宝庫ともいえるものです。
でもその出来方や来歴を超えて全てが手のひらに載るくらいの大きさとその丸みに一体として見てしまいがちです。
実はその個性は全く違う中で、同じ河原の中で、水の流れに揉まれて同じような形になって姿を見せるところは、まるで生まれも育ちもバラバラな個人が同じ器、同じ環境で同じような価値観を持つように至る会社人材のようにも思われます。
そして二つ目の質問が写真3のようなさざれ石です。
そうです、君が代の歌の中にあるさざれ石は日本のいろんなところで見られるのですが、漢字では細石とも書いて、基本的な組成としてはそれぞれの細かい石の間に炭酸カルシウムなどの石灰岩質のものがその隙間を埋めてまるで一つの巌の塊りになったようなものです。
まさに、会社の人材が同じ目標や価値観を持つことによって、それぞれの隙間に共通の意識で固めて大きな固まりとなったもの、つまりそれが企業の強さに繋がるのなら、小石の力も大きいものと変貌する良い例かと思います。
会社やグループの中にいくつもの個性があり、その特徴を最大限生かしつつも、同じ組織の中で一つに固まる理念や価値観を共有する集団としての理想をさざれ石に求めてしまうのも趣味の延長かもしれません。
「趣味は何ですか?」
人と会って話していると、時としてこのような質問を受けたり、逆にこちらから聞いていたりすることがあります。
でも改めて返事をするのはその都度同じ答えで無かったりもします。
「特に趣味と言えるものは無いですね。」
「ウォーキングや軽登山、いわゆるトレッキングにはまっています。」
「まあ、飲むのが好きなのですが、特にワインに凝っています。」
「旅行が好きで日本全国行っていない県はもう無くなりました。」
「読書が好きで特に歴史モノや経済モノはよく読んでいます。」
「休みの日は家で借りてきたDVD(今や古いでしょうが)を連続で観るのが好きです。」
「季節によって太ったり痩せたり、いわばダイエットが趣味かなぁ?」
などなど、果たしてそれらは「趣味」なのかどうか。
いつ、どこででも絶対に気になって関心があることが本当の「趣味事」だとするなら、上記以上に私の場合は「石」ではないだろうかとも考えます。
このコラム「石のことば」を書かなくていけないからかもしれませんし、仕事人間だからかもしれませんが、ついついこの石は○○石、産地は○○国、この石碑に彫られているのはいつの時代、どんな人の生きた記録か、など何処に行っても歩いていても石を目にすると考えてしまうのは、「趣味」と言っていいのか、「病気」と呼んでいいのか。
でも気になるのは、やむを得ないですよね。
ただ最初にあげたいくつかの「趣味の答え」ですが、やはりそれらもすべて私にとっては大事な瞬間瞬間です。
「ワイン」は食と共に身体に活力と満足を与えてくれます。
「トレッキング」は老いた身体の体力維持や筋力アップをはかってくれます。
「旅行」は新しい発見と自身の世界を広めてくれます。
そして「読書」や「映画」鑑賞は考え方の筋道を正し、頭の中のヒントを気付かせてくれます。
とまぁ、勝手に自分の好きなことを「趣味」と無理やり結び付けて、自分なりに納得しています。
仙台のお城と言えばだれもが青葉城と答えるかと思いますが、実は今の常識で言うお城=天守閣のある建物は無く、本丸は平屋建ての御殿があるだけでした。
その本丸御殿も明治維新で仙台藩が賊軍になったことから明治新政府から解体の命が出て撤去してしまいました。
青葉城のイメージとして大手門前の隅櫓の写真が良く使われますがこちらは第二次世界大戦の仙台空襲で焼失したものを昭和42年に再建されたものです。
しかしそれも令和になってから現存していたものと違うという史実から今後15年かけて大手門と隅櫓を再建することになったようです。
つまり政宗時代から続く建物は一切なく、基本的に江戸時代から続いて継承されたものは石垣だけです。
こちらの写真は本丸御殿前の最も重要な石垣ですが、高さがなんと17メートル、傾斜角度は70度という事で、勿論ここを登って攻めることは不可能であるばかりかこれを作るのもかなりの難易度だったと思います。
しかし実はこちらも歴代の藩主がその都度修繕、改築してきたことが近年分かりました。
というのも、前回の東日本大震災ではなくその前の昭和53年の宮城県沖地震で一部崩れかけた石垣を20年近くもかかって予算を捻出し何とか解体を始めたのが平成10年になってからで、その時に9,189個の石材を番号を付けながら解体し、元に戻すのに10,332個の石を元に戻して修復した時に、もっと内側に政宗時代の石垣跡と思われる遺跡が出てきました。
そちらは今回そのまま埋め戻したようですが、そのように何度か石垣を拡げ、高く、より傾斜をつけ、より堅固に作り直して来たようです。
平成10年からの修繕は平成16年まで6年もかけて行われ、不足した新規石材は1,699個にも及びました。
実はこの石垣はもともと仙台市内の国見地区という所で採れた玄武岩系安山岩でしたが、もはやその国見地区は住宅地となり石材採掘などはとんでもないことで、日本中を探してその新規の石材1,699個を集めたのがこの石垣です。
今の技術でもその数を集めたり修復にこれだけの時間がかかるものを、江戸時代にどのようにして採掘、運搬、加工、設置したのか、まさにロマンを感じます。
最後にこの青葉城址ですが、私の散歩コースでもあり、仙台中心部から片道で45分、歩数で6,000歩、距離は4.5キロメートル、高度差115メートルのエクササイズはちょうどいい感じで汗をかくルートになっています。
今回は徳島鳴門海峡に隣接する、世界的にも珍しい美術館の話をしたいと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、大塚国際美術館。
失礼ながら、馬鹿でかくて西洋名画のコピーを多くを展示している、模倣の陶板の絵が飾ってある美術館?のようなイメージが大半かと思います。
実は私もここに行くまではそれほど関心も持たず、興味を惹かれることはありませんでした。
愛媛県、高知県、香川県と来て最後の徳島県はどこに行こうかと考えた時に最初に出てきたのが、ここ大塚国際美術館です。
調べてみると、薬品の大塚製薬グループ、家庭用の商品ではアース製薬と言えばいくつかの商品を思い浮かべるかと思います。
その大塚グループの創業の地が徳島県で、それにまつわるエピソードがあってこの地に美術館を建てることになったそうです。
実はここ鳴門海峡からは白い砂がたくさん採れます。
それに目を付けた大塚グループの建材部門(現在の大塚オーミ陶業)の創始者が、この白砂を使って大型陶板(陶器タイルの極端に大きい物)を建築用に作りたいとの情熱でスタートしたことがきっかけとなります。
色々と研究を重ね世界でも高品質で大型の陶板の製品が作れるようになったものの、時代はバブル崩壊後の建設不況で商品の販売がはかばかしくなく、その技術の応用で写真陶板に入っていったという経過があります。
ここで、創業者の話を私が読んで共感・感動したのが次の言葉です。
「白砂のままだったら取引はトンいくら、陶板になれば平米いくら、ところが写真陶板は一枚いくら、更に美術品の陶板なら一式いくらと付加価値の数え方が変わる。」
まさに、仕事をする上での指標です。
自分たちの仕事はトンなのか、平米なのか、一枚なのか、一式なのか、付加価値はどのように伝わるのか?伝えるのか? とても感心しました。
そんなことで実際にここに行ってみました。
とにかく大きい、巨大な美術館です。
先ずは、バチカンのシスティーナ礼拝堂の天井画と全く同じ絵が、同じ大きさの規模で入館者を圧倒します。
数年前本物を現地で見た者にとっては、ほとんど同じもの、敢えて違いを言えばバチカンの最深奥の心が引き締まるような神聖さと、必要以上に来館者のささやき声を注意する警備員の存在があるかないか位なもので、その全体感は十分に味わう事が出来ます。
また、ゴッホのひまわり、と言えばだれでもそのイメージはあるかと思いますが、実はゴッホのひまわりって生涯で7枚描いていて、その7枚を一堂に揃えて一度に見ることはここ以外、そして今後も絶対にありえないという事もここで知りました。
だって、そのうちの6枚は地球上のどこかに存在しているので(うち1枚は個人所有で門外不出、美術館にも貸し出しはしないそうですが)どこかの美術館に企画で全部を一堂に集めることが或いは可能としても、最後の1枚については日本人の個人所有だったものが、芦屋の空襲で焼失してしまい、写真から起こしたこちらの陶板画は残っていても現物は既にこの世にありません。
それを含めてゴッホのひまわり7枚がすべて同じ部屋で、現物とたがわず見れるのはここでしか出来ないことです。
最後は、レオナルドダヴィンチの最後の晩餐の壁画2枚です。
左が修復前の黒ずんだテーブルの上で、ワインもパンも良く見えなくなっていた絵ですが、反対側の壁画はそれを数年かかって現地補修した、テーブル上に調理した魚も見えるダビンチ創作当時のままの絵となっています。
絵画自体は本物でなくても、それをどのように見せるかによって、又写真陶板という本物の劣化に関係なく、いつまでも今を、今のまま後世に残す絵画の展示美術館ってあっても良いものだと改めて感心しました。
興味がある方は十分に時間を取って見学されるといいと思います。
愛媛県松山市にはグループ会社の店舗があり、最近はたびたび訪問するようになりました。
そうは言っても仕事の中での出張ではほとんど観光する時間はなかったのですが、仕事とは別に時間を取ってじっくり回りたいところを見たいと思い市内のガイドマップを開いてみました。
松山観光となれば必ず入っている松山城のロープウェイ乗り場から5分ほど、また多少時間があってじっくり回る観光コースには必ず入るだろう、坂の上の雲ミュージアムからも5分位の中間地点にその観光スポットはあります。
個人的には司馬遼太郎の小説が大好きで、特に坂の上の雲は何度も読み返した愛読書です。
なので、当然ながら坂の上の雲ミュージアムも松山城も2、3度足を運んでいました。
でも、その中間にある秋山兄弟生誕の地は、あまり認知も無く訪れる人もまばらな小さなスポットで、今回初めて見学しました。
この場所は本当に江戸時代の松山藩以来の秋山家があった場所で、秋山兄弟(兄の好古、弟の真之)が実際に住んでいた場所です。
その兄の好古が明治の後半陸軍を退役した後に、松山市内の北予中学校の校長先生として赴任し、その際実家を多少改装して住んでいた時の状態を再現して建て直したものだそうです。
当たり前と言っては何ですが、今の家事情から考えると小さくて狭い感じがします。
でも、司馬遼太郎が小説の中で描写している秋山好古の、人の生き様は無駄なく簡潔をもっぱらとする、というその思想が再現された家にも色濃く遺っているように感じます。
数年前にNHKの大河ドラマ特別編(12月だけ3年に亘って全13回のシリーズとして放送された)で兄好古は阿部寛、弟真之は本木雅弘、もう一人の主人公正岡子規を香川照之での役作りもかなり原作の雰囲気にイメージが合っていると思われ、改めて最近また読み直しているところです。
特に昨今の世相や特にコロナ禍の中で、何か下を向きがちで暗く気分がすっきりしない時代にこそ、司馬遼太郎が坂の上の雲のあとがきに書いた「登っていく坂の上の青い天に、もし一朶の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を登っていくであろう」という感覚をもう一度思い出して前に進める日が来ると良いと感じます。
「石の階段」って言ってイメージするのは各人各様いろいろあると思います。
初詣でに行くような近くの神社の階段だったり、ヨーロッパのお城のような一階ロビーから二階の上がる大理石の階段だったり、或いは観光地でそれぞれが体験した名所旧跡の階段をイメージする人もいるでしょう。
人によってはトレッキングや軽登山の頂上までの階段を思い浮かべるかもしれません。
日本全国でそのような石階段イメージのアンケートってあるかないかはわかりませんが、もしあったら間違いなくベスト10位以内に入りそうなのが、金刀比羅さんの石段と思います。
みやげ物屋が並ぶ下の入り口から本殿までは石段785段、今回はさらにその先の奥の院までさらに583段、合わせて1,368段とのことでしたが、足取りも軽く片道1時間弱の軽いトレッキングでした。
本当に石だらけ、石の階段、石の欄干、石の鳥居と石の灯篭、ほとんどが花崗岩と見られますが、中には安山岩系、凝灰岩系も見られました。
その多くは瀬戸内海の中の島々や琴平町近郊の石切り場から持って来たものでしょうか。
中にはあの世界一高いと言われる庵治石のハネ石を再活用したようなものまであったように思います。
これだけの石の数量をこの山の奥まで運んだ量たるや、20トンのコンテナで何万コンテナ分か想像もつきません。
当てずっぽうですが、この金刀比羅さんの石階段に使った石の重量は1万コンテナ分20万トンを基にすれば、数100万トンを超える量なのでしょうね。
いやはや1段の石の数量だけなら大したことはないですが、それが延々1,368段もあれば想像を絶するものになります。
石の総数は想像つかないのですが、階段の高さ(蹴上げ)ってほぼ決まっていて、1段の高さが20センチメートルから25センチメートルが標準なので、1,368段は奥の院までの標高差で273.6メートル~342メートルとなります。
お土産さんの辺りを仮に標高50メートル程度とすると奥の院の高さは323.6メートル~392メートル、多少階段で無い場所にも勾配があるので奥の院の標高はもう少し高い数値でしょう。
後で調べてみたら奥の院は標高421メートルにあるというので、こちらの高さは全くの当てずっぽうではなかったと安心しました。
最後にたどり着いた奥の院の正面左側の崖の岩肌に、誰が彫ったのか天狗と烏天狗の二体の石の彫刻がありました。
これがいつ彫られて何の為に誰が彫ったのか、説明も無く不思議な感じでしたが、でも今の時代、バンクシーの落書きがこれだけ注目を浴びることを考えれば、この石天狗2体ももっと喧伝されても良いかと思いました。
宇和島城、高知城ときたらやはり伊予松山城も登ってみないとなりませんね。
宇和島城もその一つでしたが、現在日本全国で昔のままに現存するお城、つまり現存12天守の一つが松山城です。
瀬戸内海と四国山脈の間にできた広大な平野の中心に標高132メートルの勝山があり、その山頂部を平らに均した場所に本丸の天守閣が聳えています。
お城好きのアンケートでは堂々3位に入ったこともあるきれいなフォルムの天守です。
また、季節季節の花が良く似合うお城でもあります。
ここにはもちろん直接天守迄行けるロープウェイやリフトもありますが、平地にある二ノ丸跡の公園から徒歩で登ることもできます。
今回は、約20分の徒歩ルートを選びました。
往時を偲べば、家臣は毎日この道を登って二ノ丸と天守閣の間を行き来していたんだろうし、いざ戦闘となればこの道のあちこちに火縄銃や槍を持った兵が隠れ敵を迎え撃つ準備をしたんでしょう。
木陰だったり曲がりくねったりとても複雑な登攀路です。
そのポイントポイントにあるのが、立派な石垣です。
松山城は天守の美しさもさることながら、それに負けない石垣の美しさ。
上へ聳え立つ様と、美しい放物線を思わせる曲線。
芸術のような石垣のラインはしばらく見とれて立ち止まってしまいます。
もしそれが敵だったら、簡単に石落としや狭間から狙われてやられてしまいますね。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.