



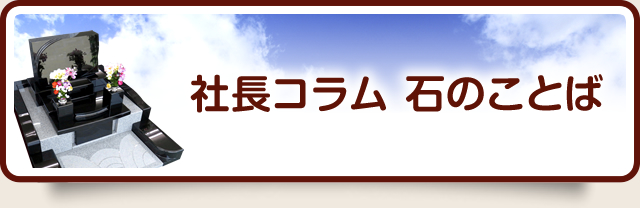
HOME > 社長コラム 石のことば
今年は誰にとっても、どんな業種の人にとっても特異な1年だったと思います。
何か下を向いてひっそりと暮らさないといけないようなそんな風潮の中で、Go Toキャンペーンが開催されたこともあり、何となく行ったことのない所を見てみたいと考え、以前から気になっていた仙台では無いもう一つの伊達藩に行ってきました。
伊達と言えば、仙台、政宗、独眼竜、青葉城、62万石などのイメージでしょうか。
ところが、もう一つ別な国持大名としての伊達藩がありました。
四国は伊予、今の愛媛県、宇和島伊達藩10万石です。
初代は伊達政宗の長男の伊達秀宗。
この秀宗という人は戦国の時代に翻弄された一生を送ります。
本来は仙台藩の世継ぎとして育てられますが、豊臣秀吉が天下人になった時に人質として大阪に預けられ、秀吉の子の秀頼とも遊び仲間として親しく成長したようです。
秀吉にたいそう気に入られ、名前も秀吉の1字を貰い政宗の宗と合わせて秀宗となりました。
ところが、関ケ原の戦いで豊臣から徳川に政権が移り、今度は徳川家の人質として生活するようになります。
以前は豊臣と親しかったので、なかなか居心地は悪かったと思います。
そんな中、政宗に次男が生まれ、そちらが徳川秀忠から1字を貰い忠宗と名乗るようになり、徳川家への遠慮からか仙台城の後継は忠宗という事になってしまいました。
ただ、それでは秀宗の行くところが無くなるので、大坂冬の陣で政宗と一緒に活躍した褒美として、政宗の計らいと家康の恩情で伊予宇和島に10万石を与えられました。
面白いのは、支藩という今で言う支店の扱いでなく、仙台伊達藩と同じく幕府が認めた直接の国持大名、今で言う別会社のトップとして国を与えられました。。
最初こそいろいろ本家の仙台藩から応援を貰いましたが、徐々に自主独立の経営をして、明治維新まで宇和島伊達藩は続きました。
更には、幕末四賢候と言われた先進的な考えを持った大名の一人として伊達宗城という賢候を出し、明治維新の序列では本家仙台藩よりもかなり格上の藩として明治のスタートを切ることになりましたが、宇和島藩初代の秀宗はもちろんそんなことは分からなかったはずです。
さて、写真は宇和島城です。
何と国内現存12天守の一つです。
石垣は他の四国のお城や、有名な大阪城などの石垣も硬い御影石で作られていますが、こちらの石垣は砂岩や安山岩、蛇紋岩などこの近くの石を集めたようです。
御影石と比べて加工がし易く、調達も容易だったと思われます。
これを見ても、秀宗の最初の頃は藩財政も大変な苦労の中、質素倹約で立派に運営していったことが偲ばれます。
仙台と四国の宇和島、今なら飛行機ならあっという間ですが、往時は如何ほどの遠隔地だったか、父政宗を思い秀宗が遠く北の空を眺める日もあったことに相違ありません。
シンガポールには人種的にも宗教的にも多種多様、まさに多民族国家というべき様相があります。
特にインド人街はその中に入ったら瞬間移動してインドの街に迷い込んだような雰囲気になります。
住居やお店などの建物もインド風というか、2階の窓がとてもカラフルで、インド風の細かい彩色を施していて、以前イタリアで見た漁村のだまし絵風2階によく似ています。
イタリアの漁村では生活が貧しくとても2階や3階建ての住居を建てられないのに、見栄を張ってか外壁に板1枚貼ってそこにいかにも2階、3階の窓があるように描き加えて貧しさを忘れた。
中には人の腕や頭を描いて今にも窓を閉めようとしているようなだまし絵もありました。
トロンプールイユという技法で、千葉にある世界的リゾートパークでもそこをモデルにして実際にその技法で外壁が描かれています。
そのようなものかとよくよくインド人街を見るとこちらは確かに中が開いていて、描かれた窓の中のいくつかは本当に開け閉めできるようになっていました。
また、二枚目の写真でみると、本来は長屋のような棟割りの建物のようですが、1階から2階そして屋根まで縦割りで色を塗り分け、完全に外の壁も分割しているようになっています。
その彩色やデザインの見事さもなかなかのものです。
細かな彩色とデザインに感心していると、なんとその先にあったヒンズー教の寺院の前で暫し呆然。
極彩色と超細密の融合、これこそがインドの集大成でしょうか。
素材は残念ながら石ではなく陶器と思われますが、このインパクトは長く印象に残りました。
シンガポールの話の続きをしたいと思います。
前回のセントーサ島ではなく、シンガポールの本島の中心地には有名なオーチャードロードという一大ショッピングストリートがあります。
さらにその通りの中心エリアに、日本のデパート 高島屋があり通る人皆がそこを眺めたり買い物したりと人気のスポットでもあります。
この中には有名ブランドも店を構え、お洒落な建物で誰でも知っている場所になります。
ただ、私はこの建物を見るたびに全く別な感情を抱いてしまいます。
今から30年程前、この建物の設計が発表された時、世界中の石材会社が熱い視線と共に熾烈な競争を呼び起こしました。
というのも、この高島屋の建物(ツインビル)四方の外壁全てが赤い御影石張りで、その石材の量たるや今までのアジア圏には無かったくらいの石の数量でした。
最終的にはイタリアの私が良く知っている会社が受注し、よく知っている役員が責任者となり、また現地シンガポールにもよく知っている人が担当として数年間滞在したりと、私の会社の仕事ではなかったですが、なぜかその仕事の流れや内容が何となくわかるような気がしていました。
このプロジェクトに使われた赤い御影石はメインが2つ、一つはインドのニューインペリアルレッド、いま世界中から産出される赤系御影石の中でおそらく最も赤色を出している石種と思います。
もう一つはブラジルのカパオボニート、またの名をボニートレッドとも言います。こちらはもう少し柔らかいどちらかというと朱色といわれるような赤系の石です。
なんとこの2つの石の丁場(採掘場)が数年に亘って半分以上このために押さえられ、なかなか手に入らない期間があって、世界中の石材需給を混乱させるほどの使用量でした。
それまではアメリカの大型ビルには総石張りもあってそのような一時的な石材の使用があったものの、アジア圏ではほぼ最初の事例、その後日本でも東京都庁などすさまじい石材使用量の烈しい大型ビルが乱立しますが、我々にとっては世界がこんなにつながっているものかと驚くばかりでした。
バブル時代の華やかさと、豪華さと、それに伴う懐かしさと羨ましさと・・・そんな数々の感情と共にその高島屋の外壁を見ると、もう一つの感情、人々の喧騒の後の寂寥感、そのような感情はおそらく私しか思っていないだろうという孤立感と共に感じてしまいました。
その理由は言うまでもなく、当時のイタリアの責任者も、多くの担当者もこの業界を去り、またこの世を去って残っている人はもはやほとんど現存せずに、誰も居なくなってしまった。そしてそのことを知っている人ももういないという、その侘しさ、儚さが先に来てしまい、どうしてもこの高島屋外壁には私だけの感情がこもってしまう、そんな思いをシンガポールに行く度、見上げる度に抱いてしまう不思議な建物です。
しばらく前にシンガポールに行った時に、偶然通りかかった場所が路傍の芸術展示場のような場所でした。
何度かシンガポールには行っていましたし、いろんな場所で芸術のあふれる都市とは思っていましたが、今回はなんと誰も人が歩かなそうな裏の道(あまりいい表現ではないですね)でのことです。
今まではシンガポールの本島に泊まってセントーサ島は日帰り、と言ってもまるで陸続きですので、ちょっと立ち寄る程度の近さですが、今回はセントーサ島にロングステイし、島内のバスやアクティビティで裏から裏まで歩き回り見て回りました。
普通なら、スカイウオークという眺めのいい舗道を往復するのですが片道だけそのスカイウオークで、そして帰りは坂を下って普通の道を戻って来た時の「裏の道」で見たのが写真の路傍芸術です。
ライオンも、昔ながらの住宅もただの路傍の石にペイントでいかにも、まるでもともと造ったように描かれていますが、本当に回りにそのままある石を、そのモノの形を生かしてペイントしたものです。
おそらく無名のアーティストの作品とは思いますが、この自然物を見ての発想が面白いですね。
最後に、降りてきた坂を振り返ったら、何と単純な平面の坂のはずが、大きな波に翻弄される帆船がたくさん!!
坂を降りてくる間はアスファルト道路に書いた落書きか何かと思っていたのですが、下から見上げるとそこには嵐のようなビッグウエーブが・・・・
何か裏の道の回り道にも、こころ和むほっとする一瞬でした。
前回号で、予約後シャトー訪問して、担当者にそのシャトーのすべてを見せてもらった話をしました。
実は、外からだけならそのシャトーの畑も、中には入れなくてもシャトーの建物や工場の外観を見ることはできます。
やっぱり、ボルドーに行ったなら、第1級の有名所を見たくて仕方なかったので、メドックエリアを車で探し回りました。
見渡す限りにブドウ畑が続き、しかも前号で紹介したように小石混じりの畑です。
ただその石も大きかったり、丸かったり、砂利だったりと大きさもその畑ごとに微妙に違いますし、専門的に言うと石灰岩系だったり花崗岩系だったり、安山岩質だったりと石の性質も違っていました。
同じブドウ品種でもワインの味が千差万別で変わってくるのは、醸造方法の違いも大きいですが、その大地の差(テロワールと言われます)が大きいことが目の当たりにして理解できました。
話は戻り、そして走っていること30分ほどで、小さな村の教会とその裏の墓地が視界に入ったと思ったら、その先に見たかった第1級シャトーのシャトーマルゴーの建物が見えました。
案内はないものの、勝手に(すいません)敷地内に入って向上外観、シャトー外観を見、そしてブドウ畑を見たら、なんとそれまで見た畑の中でも最も地味の貧弱な、近くに墓地が出来た理由もわかるようなとても畑としては耕作できないような、まるで荒れかけている?ような畑こそが、あこがれのシャトーマルゴーの畑とのこと。
説明を受けていないので何とも言えないですが、前号のとおり、良いワインは所謂地味の肥えた伸びるに容易い土地からではなく、育つに難しい中で成長したブドウこそがフランス一美味しいワインの原料となるのですね。
こちらは残念ながら、大人買いする機会も金銭も持ち合わせておらず、心残りでした。
フランスはボルドーまで来て、行かないでは済まされないのが、ボルドーワインのシャトーの訪問です。
ボルドーメドック地区には凄まじい位のシャトーがある中、その存在に権威があり、しかも世界中に知られているのが、メドック1級から5級までに選ばれたたった61カ所のシャトーに入っていることです。
第1級は誰しも知っている5大シャトー、シャトーマルゴー、シャトーラトゥール、シャトーラフィットロートシルト、シャトームートンロートシルト、シャトーオーブリオンの5つ。
第2級は14シャトー、第3級も14シャトー、第4級は10シャトー、そして第5級が18シャトーで全61となります。(ソムリエ試験を思い出します)
その中で名前が似ていて覚えるのに苦労したのが、先程の第1級の2つのロートシルト。
その他に2つのピション、ピションロングビルバロンとピションロングビルコンテストラランド。
2つのローザン、ローザンガシーとローザンセグラ。
そして今回訪問した3つのレオヴィル、レオヴィルラスカーズとレオヴィルポワフィレ、レオヴィルバルトン。
(すいません、ますます専門的になりソムリエ試験第1次問題になりました)
実はこの3つのレオヴィルも元は一つの大きなシャトーだったのが、時の権力者のナポレオンにより小さく分割されたものだそうで、その3つとも第2級格付けとなっています。
他の名称が似ているシャトー同志も、昔は同じだったものが兄弟で分けたり親せきで分割したりというのが多い様です。
今回このレオヴィル、特にシャトー3兄弟とするなら真ん中にあたるレオヴィルポアフィレに行ったのは、シャトー見学はとても人気があり、数か月前から予約を受け付けていてとても急には入れるようなものでなく、今回何とか見学の許可をもらったのが、比較的目立たない日本でも知っている人の少ない子のシャトーでした。
こちらもそうですが、ワインの産地と石は切っても切れない仲で、写真のとおりブドウ畑は小石が表面を覆う、農地としては最悪の場所です。
でも、それこそがブドウの生育を阻害することによって逆に強みを引き出し、ワインとしての深みを醸し出す大地の力です。
逆境が人を大きく成長させることと似ています。
ブドウ畑や、醸造工場、樽詰め工場、そして保管倉庫を回って最後に試飲、結局なかなか日本で飲めなかった格付け第2級のレオヴィルポワフィレを大人買いしてしまったのは、現地見学の熱量のせいかもしれないですね。
引き続き、ふらっと寄ったボルドーの霊園の話です。
通常墓石の材質と言えば、ヨーロッパでは大理石、近年では日本と同じように花崗岩(みかげ石)が多いのですが、さすがにフランスは大地自体が石灰岩層でおおわれているので墓石も石灰岩で作られているものが多かったです。
前回のゴヤの塔も同じ石灰岩でした。
石灰岩は花崗岩や大理石と比べると柔らかくて加工がしやすいメリットのある半面、風化や汚れカビなどのデメリットもあります。
日本でも当初は地産地消の最たるものであり、みかげ石産地以外では安山岩や粘板岩、凝灰岩や砂岩までお墓として使われていた地域もありました。
最近は加工の技術が大幅に高まって、最も固い花崗岩のお墓に、更にポイントや花を供えるような意識でみかげ石のアクセントお供え石(メモリアルプレート)が至る所に置かれていました。
日本で言う塔婆の感覚なのか、亡くなった時だけでなく、命日などのタイミングでお供えするようで、人種国柄に関係なく、亡くなった家族を供養する心根は皆同じなのですね。
今回はボルドーのワイナリー見学も予定していたので、ボルドー市内に宿泊しました。
時間があれば近くの霊園を見ることがまるで趣味のようになってしまいましたが、そんな中でも得るものがあるので、やっぱり行ってしまいます。
ボルドー市内のシャフトハーズ修道院に併設する霊園を予備知識も無く訪れました。
この霊園にはフランシス・デ・ゴヤのお墓があるとの説明を受けて、割と大きな敷地でしたが、特徴を聞いて探し出しました。
画像真ん中の塔のようなお墓にゴヤの顔と名前が彫ってあります。
区画的にも目立つ場所でさすがに、著名な画家だけのことはあります。
ゴヤはもともとスペインに産まれ、宮廷画家としても知られ、裸のマハ、着衣のマハなどの作品を今に伝えています。
晩年にスペインから亡命しこの地ボルドーで生涯を終えました。
そしてこの地に埋葬されたそうですが、なんとその後スペインの親族から遺骨の引き渡しを求められ、今はスペインのマドリッドに眠っているそうです。
またその時に、頭蓋骨だけ盗難にあっており、スペインには頭蓋骨無しの遺骨だけが返還されたとのこと。
なぜ、ゴヤの頭蓋骨が盗まれたのか、だれの仕業か、今どこにあるのか、全て謎だそうです。
誰かが思いついてミステリー小説になりそうな事件だったのではないでしょうか。
パリを代表する建造物は何と言っても凱旋門でしょうか。
パリ市内を南北に分けるように東西に流れるセーヌ川に沿って、その北側を川沿いにルーブル美術館ーコンコルド広場ーシャンゼリゼ通りと西側(西西北)に進んでいくと、壮大なエトワール凱旋門が現れてきます。
これはあのナポレオンが1805年にアウステルリッツの戦いで、ロシア・オーストリア連合軍を破った記念に1806年に建設を命じたもの。
ただし完成したのは30年後の1836年でその時にはすでにナポレオンは亡くなっていて、1840年にナポレオンの改葬の為、本人の亡骸が通るという皮肉と、完成後初めて大行列でこの凱旋門を通ったのが当時敵国だったヒットラーが最初という二つの曰く付きの凱旋門です。
この凱旋門の石材ももちろんフランス特産の石灰岩ですが、フランスではそれほど産地にこだわらないのか、詳しい場所はわかりません。
フランスの大地自体がブドウの生育に重要なミネラル台地であり、特に石灰岩の地層が各所にあるため、凱旋門の石の産地もそのどこかなのでしょう。
有名なのはワインの王様と言われるブルゴーニュのコートドール地区には世界有数のワインの畑があり、赤ワインのピノノワール種の最高の土壌と言われていますが、ここは有名な石灰岩の採掘場でもあり、ライムストーン(石灰岩)として海外にも数多く輸出されています。
同様にスイスとの国境近くにジュラ地区という、恐竜時代の命名の由来となった場所も、ワインと石灰岩で両方とも世界に輸出している場所もあります。
それほどフランスでは石灰岩が一般的で、建築素材としても極めてポピュラーなものと思います。
そんな中でもいろんな石灰岩の種類があるのか、パリ市内モンマルトルの丘の上にあるサクレクール寺院の製材も同じ石灰岩ですが、雨と日光の作用で汚れが落ちる性質を持っている石灰岩であると、説明がありました。
確かに同じ材質の石灰岩ですが、中の方の雨や日の当たらない場所は長い年月で汚れが目立ち黒っぽくなっているのに、外の方は日や雨にあたる部分を中心に白くきれいなままです。
外壁は定期的に掃除しているのではないの?と思って質問しましたが、それなら中もやります。ってキッパリ言われて確かに、自然の中での洗浄作用があるんだと思いました。
でも、日本の気候の中で、その湿度の中で、それが効果あるかどうかはわかりません。
特に、砂岩や石灰岩など水を吸いやすい石材に、そのような自然洗浄の機能があったらこれは素晴らしいですね。
薬品などを使わずにそのような機能を持った石材があれば日本の建築風景も変わってくるかもしれません。
(もちろん吸水率の低い花崗岩や、石灰岩と比べるとかなり吸水性が低い大理石は、日本の風土でもそれほどは汚れないことを注記として述べておきます。)
前々回はルーブル美術館の地下の石垣について記載しましたが、美術館自体も展示作品の多くも石材が大きく関与しています。
美術館の床や壁はもちろん、展示作品の台座にも素晴らしい大理石が多用されていますが、今回は有名な展示作品を石の方から見てみたいと思います。
ルーブルの石彫刻で最も有名なのはミロのヴィーナス像でしょうか、なぜかこの両腕の見つかっていないこの像が完全な比率を表す黄金比の代表的作品と言われています。
実際の石像の身長自体は2メートルを超えて巨大なのですが、その比率を現代女性或いは男性の身長に比例縮小すると、見事なバランスの体躯になるとか。
特にへそから上と下のバランスや、ウエストやヒップ、顔の大きさなどモデル並み(最近はいろんなモデルさんもいるので適正かどうか?)で、美の究極だそうです。
この石像は今から約200年前の1820年に当時オスマントルコ領だったミロス島の農民が畑で見付けたもので、興味を持ったフランスのルイ18世によって買い取られ、ルーブル美術館に寄贈されたものだそうです。
この石材の産地はほぼ特定されており、同じエーゲ海諸島の中のパロス島の白大理石と言われています。
両腕の所在を除くとほぼ完全な形で出土したこの像は、想像するにこのミロス島で加工されたものでなく、石材産地と彫刻加工の集積で産業化していたパロス島で採掘、加工、仕上げをされた後に船の運搬と陸上の輸送でミロス島に細心の注意で運んだものと思われます。
制作時期は今から2100年以上前の紀元前100年位と言われています。
もう一つの有名な女神像 サモトラケのニケ も同じくエーゲ海諸島で見つかっています。
こちらは発見自体は1860年頃だったのですが、発見時はほとんどが石の断片で数百個の端材をつなぎ合わせて今の形にしていった技術と情熱に驚きます。
大きさはミロのヴィーナスよりも余ほど大きく女神像だけで3メートル以上もあります。
それに加えて女神像の台座、その下に軍船の土台とさらに全体の台石と合わせると5メートル50センチ以上の大迫力です。
こちらの石の産地は特定されており、女神像はミロのヴィーナスの産地と同じパロス島の白大理石、船と台座の石はロードス島のラルトスという採石地から出る灰色の大理石という事までわかっています。
この場合、発見されたサモトラケ島で加工したのか、それともパロス島で白大理石の女神像、ロードス島で灰色大理石の台座を作って、サモトラケ島で合体させたのか、或いはどちらかの加工先進地に原石を移動したのか明確な答えが無いために、逆に個人的にいろいろと想像をして楽しんでいます。
こちらもミロのヴィーナスよりさらに100年以上古く、紀元前200年から紀元前300年の間というからすごい古いお話です。
最後の写真は石のはずが石でなく、エジプトのはずがエジプトでなく、四角錐のはずが逆四角錐という、何とも不思議なルーブル美術館名物ガラスの逆ピラミッドの写真です。
ピラミッドもご存知の通り、黄金比率の数値であふれています。
本当ならここにも少しだけ4000年前のピラミッドの石をアレンジしてくれたらもっと繋がりを感じたかもしれません。 蛇足ながら。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.