



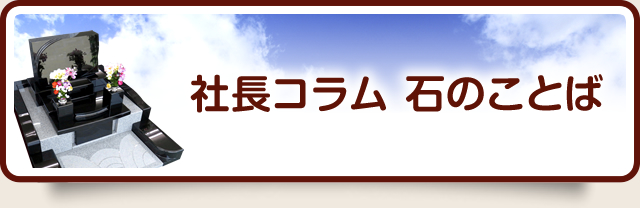
HOME > 社長コラム 石のことば
パリ市内から南に車で30分程行った所に、ヴェルサイユ宮殿があります。
言わずと知れたフランスが最も輝いていた時代にルイ14世が場所を決めて宮殿として建設しました。
まさにフランス絶対王政時代の絢爛豪華、世界で最も華麗な宮殿です。
当時はルーブル宮殿はじめチュィルリー宮殿などパリ市内にもいくつかの王宮があり、それぞれに分散して住んでいたようですが、ルイ14世が「パリは嫌いだ」ということで、新たにこのヴェルサイユに建てたもののようです。
日本でも奈良時代は平城京・平安京に落ち着くまで王都の移転が何度もあり、日本の場合理由は好き嫌いではなく悪霊や忌み事を原因としていますが、本当は旧来勢力の一新、革新的な大変革の実務的行動だったのではないかと思っていますが、ルイ14世のこの判断もあるいは同じで旧来勢力を一新し絶対君主としての権力の確立にあったのではないかと想像します。
とにかく広い敷地、水の無い土地にセーヌ河から約10キロも水道橋を引き、庭では噴水、舟遊びが出来る水量豊かな大庭園を擁しています。
こちらも近年、大修復がなされ、見学者の人気が後を絶たず(日本ではアニメのヴェルサイユの薔薇、それを題材とした宝塚のベルバラも人気を後押し)入場までに入口広場を上ったり下りたり1時間以上の長蛇を経てようやく中に入れます。
中は有名な鏡の間をはじめ、高級大理石のオンパレード。
赤い大理石はおそらくフランス南部の産出かと思っていたら、何とトールーズ近くフランス南部コーヌ・ミネルヴァ産ということがわかりました。その理由は近年その採掘場を掃除していたら、ベルサイユの中の教会(聖堂)用に350年前に発注受けて採掘したもの、途中で政変があったり計画が変わったりで掘られたまま忘れ去られていたものだそうで、フランス国内では350年振りに注文を実行する、「大変遅くなりました、間もなくご注文の品が届きます」というエスプリとともに話題となりました。
実際に4トン程の原石を届けて修復補修に使う予定だそうです。
尚、ヴェルサイユで使われた石のサンプルが、近年の修復で必要となり、それらを記念して新設された出口ホールの壁に本物の大理石が、各オリジナルの産地から再度取り寄せて一面の壁として、モニュメント的に装飾してあるのはすごく面白いアイデアと思いました。
パリと言って直ぐに思いつくのは、エッフェル塔、凱旋門、ルーブル博物館、等でしょうか。
或いはシャンゼリゼ通り、モンマルトルの丘、或いは最近の火事で逆に脚光を浴びているノートルダム大聖堂や少し離れたところになりますがベルサイユ宮殿というのも有名ですね。
先に書いたようにパリ市内自体は35年前に一度訪問しただけで、その時からの変化は大きいものとあまり違わないものとがありました。
特に35年前と比べ目立って違っているのがルーブル博物館です。
なんと外観上、今は最も有名になったガラスのピラミッドは35年前の訪問時には無かったものです。
これは今から36年前の1983年に計画が始まって1989年に完成、その後しばらくパリ市民の評判が悪く、当時の大統領批判が大きく喧伝され物議をかもしたことがあったそうです。
そういえば、130年前のパリ万博の為に建造したエッフェル塔も、歴史あるパリの風景に合わないと言われ、大きな反対運動がおこったそうですが、今はパリの象徴になっていますから、近々の評価と歴的評価の違いなのかもしれませんね。尚当時はエッフェル塔の為に景観が悪くなったという事で近隣の地価も下がり地元住民からの反対は凄かったようですが、今ではエッフェル塔に登る人が列をなし、お土産屋やカフェや観光関連の影響で土地の値段も周辺以上に高騰しています。
さて、ルーブルに戻って当時無かったガラスのピラミッドはルーブル博物館の建物自体が横長のコの字型の建物で、コの字の反対側に行くのに大きく左回りで迂回しないといけなかったのを、コの字の真ん中のナポレオン広場の真下に入口及び通路を作って、そこからならコの字の建物の三方どこにでもすぐに行けるようになるのと、常に入場口で渋滞混雑していたのをその地下入り口をメインにすることで緩和させる意味があったという話を聞きました。
そういった理由でルーブルの地下を掘っていったところ、なんとたくさんの石が発見され且つその形を復元するとルーブルは今でこそ博物館ですが、その前は王宮、そしてさらにその前は城塞であったとのこと。
お城を守るように城壁があり、その外側に水をたたえた堀があり、更にその堀も石垣で組んであって、その発掘調査の詳細や復元図は近年になって中庭発掘で初めてわかったようで、日本人から見ればまるで大阪城の石垣と内堀のような、江戸城の石垣とお堀のような感じを抱かせます。
石材は大阪城の花崗岩とは違い多少加工のしやすい石灰岩ですが、それでも大阪城と同様に一つ一つの石に十字架やアルファベットや絵文字などどの班、どの職人が加工し施工したのかの目印が残っていることも世界に共通していることかもしれません。
実はルーブルの地下にはそのように石垣のサンプルがそのまま残っており、美術館としての価値ともに歴史的建造物としても、見るべき価値がありました。
もう一つ以前に無かったものとして、ルーブル美術館の地下からカルゼル・デュ・ルーブルというショピングモールが続いていて、高級ブランドからお土産屋、カフェなどその時の地下発掘後の再活用も進んでおり、まさに旅行者には便利で複合的な集客が可能なエリアに変化していました。
ふつうは美術品を見るためにルーブルに行くのですが、石の城壁など見てる人は珍しいと思われるでしょうから、一応はルーブルの定番 ダヴィンチの「モナ・リザの微笑み」もちゃんと再会してきました。
こちらはあの時からあまり変わらず謎の微笑みを浮かべているだけでしたが。
続いてもペールラシェーズ墓地の話ですが、今度は火葬と納骨堂の話です。
実はここラシェーズ墓地の中には、火葬場が一緒になっていてその周りにたくさんの建物が囲むように建っています。
吹き抜けの回廊型の建物のあれば、完全な石の教会型のもの、あるいは地下型のものなどがびっしりと墓地の中の火葬場の回りに建ち並んでいます。
これらは納骨堂で30センチ角位の仕切りの中にお骨を入れて蓋をし、その蓋に個人の名前を刻むものです。
多少奥行きがあり夫婦単位で2名、あるいは家族単位で3名分のお骨を入れることもできそうです。
墓地と共存して数万のお骨がこの納骨堂の中で安置されています。
フランスは宗教的にはカトリックが大変に多く、人口の8割くらいがカトリックと言われています。
もともとカトリックは土葬が主体で火葬は嫌がるのですが、フランスのカトリックは比較的火葬を容認しており現在は約3分の1は土葬でなく火葬を選ぶようになってきているとか。
特に大都会であるパリでは火葬も普通になってきているそうです。
やはりこちら納骨堂タイプにも有名人が眠っており、オペラ歌手のマリアカラスはこの納骨堂の中にあるそうです。(数万の数でとてもではないが場所を知らないと見付けるのは困難で確認はしていませんが)
納骨堂は規格化された同じ形の個別墓所ですが、やはり独自性を求めてか、蓋の石に凝ったり、生前の個人の写真を貼ったり、造花やブロンズを嵌め込んだりといろいろな工夫もありました。
同じくペールラシェーズ墓地の話をしたいと思います。
とにかくここはひとつの街のように、大きな街路樹のある通りで区画が管理され、まるで住宅地のように○○通りの○○区画○○番地というように墓域が並んでいます。
大きさは多少違いはあってもさすがにフランス革命で自由平等を勝ち取った民族だけにある程度の大きさで揃っています。
ただ、お墓の形は先程のショパンの様にデザインの凝ったものもあれば、家の形の人が立ち入れるもの、あっさりとお棺の形で蓋をしたものなど千差万別です。
また、使用している石も、御影石あり、大理石あり、フランス産の石灰岩ありと見た目も材質もバラエティに富んでいます。
墓地の中を歩いていると結構な人だかりがあって、近親者の納骨かあるいは命日に墓参りかと思い、ちょっとその集団を避けて回っていこうとしたところ、どうもそんな悲しく神妙な様子はなく、明るい声で大きな話が聞こえてくるので興味を引かれてしまい近づいてみました。
するとそこは、まるで観光のツアーガイドよろしく、一人の男性がまるで関係のない人たちを連れて、霊園内のお墓巡り、有名人の墓ツアーをしているところでした。
皆で見ていたのは歌手で俳優だったイブモンタンのお墓とのこと。
あとで調べてみると、あのマリリンモンローと一時恋仲になり大きく世間を騒がせたとのことですが、お墓自体はあっさりとシンプルで材質も地元の石灰岩製でかなり地味なものでした。
そしてそのマリリンモンローと浮名を流していた時にも、イブモンタンは結婚しており結局はマリリンモンローと別れてその奥さんの元に帰っていったという事で、その奥さんも同じ墓石に刻まれていました。
奥さんも有名な歌手で女優のシモーヌ・シニョレという名前だそうですが、確かに墓碑の上に奥さんの名前、下にイブモンタンと彫ってありました。
意外な個人の歴史と夫婦の歴史が墓石に刻まれていて、それまではあまり知らない過去の人でも何か親近感を感じてしまいますね。
最後の写真は、そのままガイドさんに付いていって無料で(調べたらお墓巡りツアーは一人2000円位からたくさん流行っているそうです)ちょっとだけ聞き耳を立ててガイドさんが言っていたことです。
「この墓地はカトリックもイスラームも仏教徒も関係なく隣り合ってお墓を建てていても問題ないが、共産主義者や独裁主義者のお墓だけは隣にならないように一カ所に区切って建ててある」とのこと。
宗教の自由は認めても、主義主張はさすがに自由の国、或いはナチスと戦った国だけあってそこは区別しているところが面白いと感じました。
ただガイドツアーの皆さんもその話の後笑っていましたので、フランス人特有のエスプリなのか本気なのかはわかりませんが・・・・
今回訪れたパリは、トランジットの為にシャルルドゴール空港の乗り継ぎで降り立った以外では何と35年振りの訪問でした。
フランス自体はその後も何度か訪問しているし、上記のようにパリ経由でエアフランス乗り換えは何度もあり縁遠い国ではなく、何年か前にはある設計士の依頼でフランス南部のトゥールーズ近郊でパロマやヘンリーフォーと呼ばれるフランス産のグレー大理石の産出丁場まで石を検品に赴いたりしたので、それほど間が空いたとは感じていなかったのですが、やはり石の仕事優先となるとイタリアやスペイン、ポルトガル、ギリシャ等の有名大理石産地国の方が、圧倒的に訪れる回数が多かったからでしょう。
フランスも先ほどの南部のトゥールーズやランゲドック地方からは赤色の大理石が出ますが、基本的には石灰岩が主流で、前述の大理石も今はほとんど産出しなくなってきています。
そんな中での今回のパリの訪問で、何と最初に行ったのが、パリ市内にあって最大の面積(43ヘクタール)を誇る、ペール・ラシェーズ墓地でした。
ここは墓石業界、大理石業界人には特に有名な場所で、何人もの著名な人のお墓、また大理石彫刻のデザインも精密でバラエティに富んでおり是非一度はと思っていた場所です。
ここに眠る有名人をあげたらきりが無いほどですが、一例をあげると
・エディットピアフ
・オスカーワイルド
・モリエール
・バルザック
・ドラクロワ
・イブモンタン
などなどですが、一番有名なのは大理石彫刻の素晴らしいショパンのお墓でしょう。
イタリア産と思われる白い大理石の女性像が象徴的で、台座にはショパンの顔のレリーフが彫りこまれています。
訪れる人が絶えないせいでいつも周りには花が供えられています。
ショパンは偉大な音楽を遺したと同時に、素晴らしいお墓の継承で現代の人々にも感銘と驚きを遺してくれているのですね。お墓のあり方が改めて問われていると感じました。
写真①はたくさんある入口の中のメイン 正面出入り口
写真②は墓地全体の地図とここに埋葬されている有名人の名前と場所
写真③はショパンのお墓
「スペインに一日しか居れないのならトレドに行くべきだ。」
「トレドは街全体が博物館である。」
と現地の人に言われて、マドリッドから車で1時間ほどの古都トレドに行きました。
ここは初めは西ゴート王国の首都として繁栄し、スペインの都市国家間の割拠時代もトレド王国の首都として近隣ににらみを利かし、またスペインにイスラム教が入ってきたときにもそれなりの存在感を持ち続けていましたが、近代のスペイン王国統一時に首都機能としては小さ過ぎて多くの人口を収容しきれず、平地でいくらでも拡大できる今の首都マドリッドに移ってからは、人知れず中心地としての地位が無くなってしまいました。
日本で言うと、東京から言う所の鎌倉の地であったり、京都から言うと奈良の地と言ったところでしょうか。
とにかくここは写真のように、自然の川の流れを外濠として大きな丘全体が城郭都市のように近隣の平地を睨んで聳えています。自然の岩や地形をうまく利用して石の城壁を組み、外敵からの守りには絶対的な要塞となっています。まるで大坂冬の陣で惣堀を埋められる前の秀吉建立時の大阪城のように難攻不落の城塞だったと思います。
現に1930年代の第二次世界大戦の先駆けとなったスペイン内戦時にも、この地形を生かして近代兵器でも陥落させることが出来なかったそうで、まさに昔の人の場所を見る目は古今東西、世界中で共通しているのかもしれません。
このトレドの中央部丘の上に、大きな教会があります。
トレドの大聖堂として観光案内にも載っていますが、ゴシック建築の大聖堂で高さを競い、尖塔を持つ教会ですが、面白いことに教会の製作年代が数百年間に及んだせいで、外観も内部も左右対称でなく、途中でルネサンス調を取り入れたり、イスラム教時代のアラビア様式が入っていたりと、何とも東西や年代の融合した建物となっていて面白い大聖堂です。
ここは内部の写真撮影も一部を除いて許可されていて、スペイン人のおおらかさや、こだわりの無さを感じます。
おおらかと言えば、トレドの大聖堂内にある黒い肌のマリア像もスペインの特徴かもしれません。
黒い肌のマリア像で最も有名なのはモンセラット山のマリア像ですが、そちらも同じくスペイン国内にあります。スペインはモロッコや北アフリカに近く、またアラブの人々とも交流があり、北ヨーロッパの人たちのように肌の色に異様にこだわることが無いのかもしれません。
そして、トレドの芸術家と言えば何といってもエル・グレコです。
元々エル・グレコはギリシャに産まれましたが、ここトレドが気に入ってトレドに居を構えて活動をしていました。
その為か、この大聖堂にもエル・グレコの宗教画がたくさんあります。
最後の写真は、エル・グレコのキリスト磔刑の絵ですが、当時の宗教界、美術界を騒然とさせ、多くは異端であるとされたものです。
理由はお判りでしょうか?
答えは敢えて書きません。
ヒントは色と光です。
続いて、ガウディの住宅設計の実例を紹介します。
写真1はカサ・バトリョ(バトリョ邸宅)です。
バルセロナ市内の中心地にあるカサ(邸宅)ですが、邸宅とはいえ日本なら数世帯、数十世帯が住むことが出来る中型マンション一棟分くらいの大きさです。
世界遺産に登録されてからは、一回当たりの入場制限もあり、中の見学ではこれだけ並んでないとは入れないです。
外壁のファサードは砂岩を加工した石柱で、地元では骨の家と言われているそうです。
また、外壁上部にはタイルが外壁一面に貼られて、設計上はグエル公園から流れを汲んでいながら、更にそのタイルに厚みや重なりを持たせ立体的な表現をしています。
バルコニーは仮面や骸骨の顔をイメージさせ、合わせて色ガラスで目や顔の雰囲気を更に醸し出しています。
個人的にこの建物に住みたいかどうかは意見の分かれるところと思いますが、、とにかく世界観が変わりますね。
次の写真2は、なんとも奇抜な直線が一切無い,曲線だらけの建物、カサ・ミラ(ミラ邸)先程のカサ・バトリョから歩いて5分程のほんの近くにペレ・ミラ氏の邸宅として設計された個人邸です。こちらも先程のカサ・バトリョ同様、6階建てか7階建てか個人邸とは言えマンション一棟分の大きさです。そしてこちらは固い花崗岩(御影石)を多様した外壁で更には直線を使わず、曲線だらけ。石屋としてもっと驚くのはその石は原石を積み上げた塊りも構造材になっていて(日本のビルは表層を石で貼る装飾材です)まるで、石の採掘場(丁場)がそのまま建物を形成しているような感じです。
そして屋上に上ると、もっともっとびっくりです。
写真3はその屋上の何とも奇抜な風景です。
皆さんは何を感じますか?
どんな感覚が生じてきますか?
屹立している細い尖塔のようなものは砂岩を使った煙突で、屋上屋を重ねるようなごつい小屋のようなものは階段の出入り口のある階段室、この景色だけは現地で実感しないとその迫力を説明しるのは難しいかもしれませんね。
でもこの景色がカサ・ミラの屋上に上がると突然現れ、その衝撃たるや、少しでも読者の皆様に分けて上げられればと思いますが・・・・
とにかくこのカサ・ミラの花崗岩の外壁と屋上の異空間は一見の価値ありです。
バルセロナ、ガウディ、で連想されるのは、ほとんどの方がサグラダ・ファミリア(聖家族教会)だと思います。
ただ現地に行くとガウディの作品が至る所にあり、またそれぞれ文化遺産や世界遺産に指定されており、見るものはたくさんあります。
サグラダ・ファミリアに続き数カ所ガウディの作品を見ていきたいと思います。
バルセロナの市街地から程近い少し高台のあたりに、グエル公園というのがあります。
ここは、バルセロナの実業家であり富豪であったエウゼビ・グエルという人がバルセロナの人口拡大に合わせて、裕福層の人々の新興住宅地として、当時禿げ山だった地区を買収し、ガウディに全体の都市設計、都市計画を依頼したのもです。
先にこの大規模事業の結果だけを言うと、新興住宅地としての販売に関しては失敗でした。
団地の入り口の門番の家や団地入口のエントランス、カトリックの協会、住民共有の広場や多目的共有施設、雨にあたらず人が通れる回廊や、自動車や馬車の通れるメイン道路など居住区以外はほとんど完成して、超高級住宅地としての体裁は整ったのですが、肝心の販売用の分譲宅地はバルセロナの法令もあり広大な各区画面積に対しては6分の1の建物しか作ることが出来ずに(日本でいう建蔽率と同じようなものか?それだと建蔽率17%???土地効率がとても悪い。)約60区画の販売予定区画は全く売れなかったようです。責任を感じてかガウディもこの中に土地を買い、家族の別荘を建てて使っていたようです。
結局、この公園はグエル氏の子孫がバルセロナ市に売却し、その後バルセロナ市営の公園として一般公開され、今はユネスコ世界遺産に登録されています。
話をグエル公園の現状に戻したいと思います。
いともすると、ガウディの作品は奇抜さやデザイン性だけに注目されがちですが、実際には実用的な観点で設計されたものが中心となっています。例えば共用広場の雨水の流れに注目し、雨樋や排水路の設計を考えて、石彫刻のライオンの口から雨が滴ってくるようにしたり、一階部分の柱の中に排水路を入れて外からは雨樋が見えなくなっていたりと、実用性や、自然を生かしたものとなっています。
また、柱の形や回廊のデザインも、単に思い付きのデザインでなく、今でいう構造計算や強度計算を独自の方法で行っており、決して奇抜さだけがガウディの本質ではないというのが、今回改めて感じました。
更には、今で言う人間工学に基づいて、人の体の曲線に合わせて、座り易い椅子やベンチ、握ってしっくりくるドアの持ち手やノブ、登り易い階段やスロープなど、直線よりも曲線を多用しています。
極論で言うと、実用とち密な計算と芸術性の融合がガウディのデザインなのでしょう。
それが曲線の多用と奇抜な色使いになっているのかと思います。
石屋からすれば、曲線はR(アール)加工があり、原価が直線(平面)の数倍の価格になります。
ご存知のように石は金属のように曲がらないので、曲面の分は平面を削って曲面研磨という、石の量も加工の技術もとんでもない作業となります。
このグエル公園はその曲面が多用されています。石の費用はどれだけかかったのだろうかと心配もしましたが、近くで見ると平面の多面体を使っている個所も多く、曲面に平らなものを幅狭めて短冊形に貼っていき、遠くから見ると大きな曲面、曲線になっている手法はそれなりに予算や工期を意識したのかと思います。
また、石と同様、タイルも曲面に張り付けていますが、それが敢えて四角いタイルを割って(一部説明では割れたタイルや余り物を好んで安く購入して)多面体としてアールを作っていて、タイルの割れた感じと余り物を使った(と言われているが果たして疑問ですが)色のバリエーションが、更に芸術性を高めているのかもしれません。
現代の建築家や設計や、建築に携わる人たちにとっても大変参考になるものです。
スペインと言えば、首都はマドリッドですが、観光で有名なのは何といってもバルセロナでしょう。
もちろんアルハンブラ宮殿で有名な南部のアンダルシア地方や大理石とオレンジで有名なバレンシア地方など、魅力的な街はたくさんあるのですが、やはり一度はバルセロナは訪れたい街です。
スペイン第二の街でカタルーニャ地方の中心都市、今でもマドリッドに対してのライバル意識だけでなく、独立運動も激しく、独立の国民投票の動きまであります。
もともと主な産業は地中海貿易やヨーロッパとの交流の窓口として商業で栄え、そしていち早く産業革命を取り入れた重工業都市でもあり、スペインの中でも比較的豊かなエリアです。
そのせいでしょうか、マドリッドにはお金持ちも多く、街つくりや建物にお金をかけていいものを作り、そして競い合った様子が見られます。
その最たるものがあの有名なサグラダ・ファミリアでしょう。
これに関しては今更私が何をかいわんやでしょうが、サグラダ・ファミリアの石について述べたいと思います。
遠目で見ても、これが石なのか?、大理石でよくあんなに高いところまで?と疑問をもって近づいていくと、外壁の多くは彫刻のしやすい砂岩や安山岩、一部に大理石や花崗岩もありますが、イタリアの大聖堂の総大理石造りとはやはり感じが大きく違います。
石の重量の問題や、聖書の物語を外壁に表すための細かな細工など、やはり花崗岩やオール大理石では難しいところがあったのでしょう、風化の割合の早い砂岩を多用し、そしてその隙間には石との相性を考えてセメントも使っています。(但し内部は花崗岩と大理石とステンドグラスで、外観とは全く素材が違います。)
そのせいかどうか、前に建てた尖塔と最近作った尖塔では風化によって色が変わってしまっています。
それもそのはず、このサグラダ・ファミリアは今から130年以上前に建築がスタートし、ここからさらに10年以上かかると言われています。130年前の石の色と今の色が違うのはたとえ同じ採掘場の石でも違って当然でしょうし、初めの砂岩は既に風化が始まりつつあるので合わせようがありません。
長い年月をかけてここまで出来るのは、単に設計者のアントニオ・ガウディの情熱だけでなく、それを支えたバルセロナの市民や関係者がつないだ熱意なのでしょう。
ここまで来たら、完成はゴールでなく、作業し続けて未完成のまま続けることが目標となってもいいのかもしれません。
今回の霊園巡りはスペインの、アルムデナ霊園の視察です。
ここはスペインの首都、マドリッドの市内にある、広大な敷地を有する霊園です。
ヨーロッパで最大と言われ、ショパンやビゼーのお墓があるパリのペール・ラシェーズ墓地と肩を並べるくらいの広さだそうです。
さて、初めにその霊園を訪れて感じたのは、「おとなしい」墓石が多い、「地味」な霊園という感想した。
特に、マドリッドに入る前に数日バルセロナの「派手で」「前進的な」街に居たせいかもしれません。
ご存じのとおり、バルセロナはガウディを先頭に、建築デザインや都市設計で世界に先行し、またピカソ美術館もあって芸術でも奇抜さや先進性を好む地域です。
ところがこのマドリッドの霊園の石は、ほぼ白御影石でうめつくされ、目立つ黒やカラフルな赤、ピンクなどの色はほとんどなく、またイタリアで見られるような大理石も少なく、「単一な」感じです。更には墓石の形もカトリック信者がほとんどと言われるスペインですので、十字架を模したお棺型の墓石でほぼ統一されています。
まさに奇をてらわず、デザインに凝らず、一般的な形を好む、伝統的な生活を送る、クリスチャンの生き方が墓地にも表れているように見えます。
尚、カトリックですので、埋葬方法もまだまだ土葬が多いですが、土地の有効活用のため、今は家族墓として活用されており、土葬のお棺を二重三重に重ねたり、一部は火葬で焼骨を収めていることも増えているようです。
いずれにしても、スペイン=バルセロナ=斬新 という思い込みは全く違っており、マドリッドは少なくとも日本の田舎のように、お墓に関しては伝統と旧守型の、地味な墓石事情を実感してきました。
(残念ながら、斬新的な感覚のあるバルセロナの霊園や墓地は今回見れませんでしたので、街並み同様に「地味な」マドリッドの墓地と比べて、果たしてバルセロナの墓地や墓石が「派手で斬新性が」あるのかどうか、次の機会に調べて来たいと思います。)
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.