



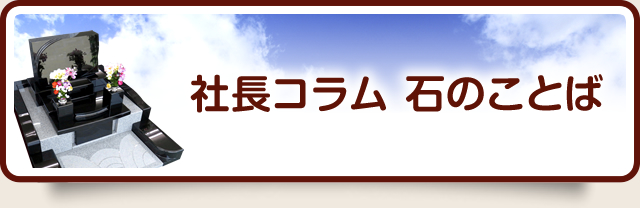
HOME > 社長コラム 石のことば
ナポリ近郊で、ポンペイの次に訪れたのはアマルフィです。
このアマルフィ、日本で急に脚光を浴びたのは織田裕二と天海祐希が主演した映画「アマルフィ 女神の報酬」が一躍脚光を浴びたのが理由と思いますが、こちらイタリアでは既に中世から4大海洋都市として有名で数百年栄えた共和国でイタリア全土でもとても有名な場所でした。
4大海洋都市とは、アドリア海側のヴェネチア共和国、そしてティレニア海側(メデテレーニア=地中海側)にあるジェノヴァ共和国、ピサ共和国とこのアマルフィ共和国です。
この4大海洋都市は今でも船の競技大会を開催しており、お祭りとして和気あいあいで楽しく、かつ一部は昔に戻って競技・競争のように、時に戦争のように真剣に開催されているそうです。
今では超高級な別荘地、プライベートビーチを備えた高級避暑地であり、こんな平面がいくらも無い崖地の中に店も人もあるれるように闊歩しています。
少し一般の建物とは異質な感じがするのはアマルフィ大聖堂(ドゥオーモ)です。
ローマやフィレンツェの聖堂は、街に完全にマッチしてその様式に違和感が無いのですが、ここアマルフィの聖堂は、何か周囲の建物との異質感があります。
理由はおそらく建築の様式やその色使いで、何となくビザンチン様式やオリエント風な色彩のせいかと思います。
海洋貿易国家であり、広くギリシャやトルコ、或いはアフリカ大陸の北岸も含めいろいろな文化と交わってきた何よりの証しではないかと思います。
またそのドゥオーモ広場の噴水も、ギリシャ彫刻やローマ彫刻の流れを汲みながら、水と乳を大切にする砂漠の民(イスラム民族やユダヤ民族)の意識も含まれて、いろいろな地域の文化がごちゃ混ぜになった何かユーモアを感じる石像だと思いました。
引き続きポンペイの遺跡と石の話をしたいと思います。
写真 が中央広場のアポロ神殿の石柱です。
大理石よりは少し柔らかい石灰岩製ですが、円柱の加工も、それを二階建てに設置する技術は近代文明でも現代でも今もって難しい作業です。
まあそれを言ったらアテネやミケーネなどもっと歴史の古いギリシャ文明、エーゲ海文明時代でも大理石の神殿が至る所に在ったわけなので、人類と石との関わりの古さとその技術や情熱には改めて驚かされます。。
ここで余談ですが、各地の遺跡は何故か柱や壁は残っていても、屋根がほとんど無い、或いは全く残っていないことが共通しています。これは屋根材として重さの関係もあり石が使われていないのが理由です。
日本の玄昌石(スレート)のように石材を薄く加工し軽くして屋根材として用いる(玄昌石の屋根材で有名なのは東京駅の駅舎屋根です)事もあるとは思いますが、それでもその石を置くための桟や梁などはやはり燃えて消失してしまう事のある木材や、或いは錆びて強度が無くなる事のある金属類で造ってあり、全てが石で出来ている屋根が無いので、歴史の中で屋根は残らず、柱や壁だけが残ってしまうのです。
前回も最後に記載しましたが、「石こそ永遠に亘ってメッセージを伝える唯一のモノ」だと確信します。
さて話を元に戻します。
この神殿の周りには役所と思われる建物、裁判所と想定されるもの、今で言う国会のような政治家が集まる建物などが密集しており、政治の中心エリアだったようです。
逆にポンペイには王宮や王族の建物が存在せず、いわゆる民主主義、或いは共和政がしかれていたこともわかります。
医術も進んでいて診察用の器具や手術用の道具なども発掘されていますし、ワインを売る居酒屋も、剣闘士が戦う円形大劇場もあり、まさに充実した個人の生活が営われていたと思われます。
写真 は演劇などが催わされたであろう半円の小劇場です。
中央のステージから客席にはよく声が響くようになっています。
また最前列は客席の椅子がギリシャ産らしい白大理石で出来ています。
後列のレンガ調の椅子と比べると当時も最前列は砂かぶり席で、高級だったのでしょう。
写真 で石の小口(脇の面)を見ると厚さ約2.5cm、座る面は今の技術ほどではないですが、ミズ磨き程度には研磨されています。
半円の劇場に合わせた石の曲線加工(R加工)も上手になされております。
当時の人々はここに座って、トロイの木馬やアレキサンダー大王の遠征劇などを砂かぶりの中で見ていたのでしょうか。
引き続き ポンペイの石の話をしたいと思います。
いろいろな出土品から想定して、当時の文明が今から2000年前の、日本で言えば弥生時代の物とは到底思えないのですが、視点を石屋の目から想像してもかなりの水準だったと思います。
写真 は室内に飾ってあったであろうモザイクの肖像画です。
色使いも陰影もそしてその写実性も、近代の油絵や芸術を思わせる感じがします。
私の個人的な呼称ですが、「ポンペイのモナリザ」と呼んでしまいました。
おそらく豪商か貴族の奥さんの肖像画で、ミスポンペイだったのではないでしょうか。
写真 はポンペイの街を縦横に走る車道です。
大きな石で全面舗装してあります。
ここには写っていませんが、馬車の車輪で出来た轍や、雨を流すための排水溝も車道には残っています。
この写真にある小さな白い石はここが車道であるという印で、夜になるとこの白い石が光るという説明を受けました。
石の種類が猫目石との記載がありましたが、もちろん宝石で言うキャッツアイとは違うと思います。
見た目ではペルリーノキャーロという大理石に似ており、おそらく貝の成分のようなものを多少含んだ大理石のような感じです。夜に光るというよりは月光や星の光でその部分がぼんやりと反射するのだろうと思いますが、いずれにしてもすごい発想です。これでだいぶ当時の交通事故を防いだのでしょう。
写真 はテルマエ(公共浴場)の中にある、大理石一体ものの水盤です。
おそらくギリシャ産大理石の大きな原石(およそ10トンくらいの重量)から成形し、中に給水用の穴をあけ水又はお湯が出るように加工し、尚且つその大きな重量物を浴槽のある室内にどうやって運んだんだろう・・・・?
かなりの技術と文明の証しです。
そして、その水盤の周辺にはそれを製作し寄贈した(当時は選挙運動用に寄付が行われていたそうです)政治家の名前がギリシャ文字で彫刻されており、今でも読めるとの事。
2000年前の政治家のポスターが現代人にアピールしているんですね。
改めて石が次世代、未来に引き継ぐ永遠の通信手段なのですね。
まずは、写真 の人物像を見てください。
どこかで見たことは無いでしょうか?
中学高校時代教科書の挿絵などに出てきませんでしたか?
ヒントは世界史、世界最初の広大な領土を持った有名な大王の肖像です。
正解は紀元前333年マケドニアの王アレキサンダーとペルシャの王ダレイオス3世の戦い(マケドニア軍が勝ちました)であるイッソスの戦いを描いたモザイク画にあるアレキサンダー大王の肖像です。
もちろん、ペルシャの王やペルシャ軍も描かれています。
発掘当初はほぼ完全な状態で見つかったのですが、保管や移動を繰り返すうちに多くが欠落してしまい、今は写真 のような状態です。
大きさは横5.82m、縦が3.13m、石は細かく2 3ミリの大きさのものを約100万個使って表わしています。
当時はポンペイの大きな商人の自宅の床に敷いてあって(ファウヌス又はファウノの家と呼ばれる)先ほども述べたようにそれを発掘して移設したのですが、何せ細かい石の分解移動は難しくかなりの部分に欠落が生じてしまいました。
それで現在はこれに限らず、ポンペイ遺跡から出土した多くの貴重品は、ナポリ国立考古学博物館に永久展示という形で床でなく、壁状で展示されています。
写真 は何と発掘当時まだ欠落前の完全な状況をスケッチした画家がいて、それを復元した彩色画です。
全て揃っていればこうだったのかと少し残念な気もしましたが、でも2300年前のアレキサンダー大王の肖像画が今に伝わる不思議さに何とも感無量の想いでした。
ポンペイは以前からどうしても見てみたい場所の一つでした。
今からおよそ2000年前の紀元79年8月24日午後1時にヴェスヴィオ火山が噴火し、その12時間後には大規模な火砕流によってポンペイの街は完全に地中となり、更にその上に火山灰が積もり忽然として地上からその存在が消えてしまいました。
ローマや他の地域からの救援もあったように記録にも残っているようですが、多くの救援者も被災しもはやどこに何が在ったのかも分からない状態で、それから1700年間完全に地上から忘れ去られた場所でした。
それが1748年に火山灰の下からかなり原状に近い形の建物群や生活の痕跡、時に高熱で瞬間に固まった人体や、各種金属類など1700年の眠りから目覚めて起きだしてきたようにその姿を現し始めました。
現地に行ってびっくりするのはその規模です。
最初の発掘から300年近く経っていますが、街全体は97ヘクタールあると言われ、その区域は にエリア分けされています。(ほぼ終了したエリアは 、 、 と 、 の半分位)
ところが発掘完了はまだその半分くらいであり、完全にその姿が出て来るにはさらにしばらくの時間が必要との事です。
当時のポンペイは非常に文化的にも進んでおり、海防・商業都市としての街の門や各種宮殿、商人の大邸宅、居酒屋、パン屋、クリーニング屋、共同浴場など庶民の生活まで分析できるような遺跡がたくさん残っています。
その理由は火山灰が空気を遮断し、金属類を錆から守ったことや、壁画の中のフレスコ画と火山灰の成分とで劣化させるような化学変化を来さなかったことなどラッキーな面もありますが、何より建造物が石であったこと、街の道路も、テーブルも、パンの窯も、風呂も石であった事が現世に残せた大きな理由です。
特にポンペイで有名なのは、床や壁に飾っていた大理石のモザイク画です。
これが至る所から当時のままで出土し、そこから当時の社会、風習、人々の暮らしなどを類推する一級の出土品になったものです。
その中には世界中の中学生、高校生が教科書等で見るあの人のモザイク画もあるのですが、それは次回に致します。
今までのイタリア訪問先はどちらかというと中部から北部が多く、いわゆる長靴で言うところの脛の部分やふくらはぎのあたりに行くことが多かったのですが、(例えではわからないかもしれないので具体的に言うと、ローマやフィレンツェ、ピサ、ジェノヴァ、ミラノ、ヴェネツィア、ヴェローナ、ボローニャなど)イタリアには「ナポリを見て死ね」という諺があり、(なぜか直接翻訳でこう言われるようになりましたが、本来は「死ぬ前にナポリを見ろ」「ナポリを見る前は死ねない」という事です。)長靴の下の方、前足首の少し上あたりのナポリ訪問の事をお話ししたいと思います。
ナポリは基本的には国も違えば、人種(?)も違うような感じです。
昔の成り立ちはギリシャの植民地で「ネオ・ポリス(新しい都市)」が語源との事で、海洋民族としてギリシャ系のルーツを持っていたり、ローマ帝国の傘下の時もあり、イスラム系のシシリア王国の傘下だったり、ようやくナポリ王国として独立するも、スペインのブルボン家(フランスのブルボン家の親戚)の支配下だったりと、人種や宗教含めいろいろな生活の価値観も混在した歴史を持っています。
気候は温暖でカンツォーネに代表される音楽も陽気で、食べ物も魚介を中心に美味しいのですが、なぜか「治安がいま一つ…」と言われて観光客にはなかなか人気がありません。
ナポリの街の中心には真っ直ぐな線の「スパッカナポリ(ナポリを切る)」という通りがあり(写真 )、これがナポリの街を二つに区切っており、でもそこは狭い路地に雑多な店が建ち並び人が集まる超混雑地帯であると同時に「スリ」なども多い所だと言われ続けてきました。(写真 )
ただ、そんなことを言ったらどこでも雑踏の所や観光地は危険であり、きちんと注意をしていればそこまでの心配は無いように思います。
また、マフィアの支配する街とも言われますが、一般のイタリア人やナポリ人(?)、ましてや外国人観光客にとっては全く接点は生じません。
現地の人に聞いてもマフィアはマフィア同士のいざこざは聞くけど一般人には何も心配ないよと言われます。
そういう意味では治安上での特別な問題は感じません。
尚、ナポリの魅力は市内だけでなく、ポンペイやソレント、アマルフィー海岸(写真 )、カプリ島や青の洞窟などその近郊も含めて素晴らしいエリアが堪能でき、中部イタリア、北部イタリアとはまた違った魅力があることは間違いないと思います。
次回はポンペイ遺跡について述べたいと思います。
毎年恒例で例年の事ながら、当社のグループ会社が1月決算の会社から5月決算の会社まで途切れる事無く期末・年度末が続く関係で、この期間は時間的な余裕がなくなるのが常です。
コラムの執筆が滞っている事の言い訳ではないのですが(しっかり言い訳していますが)特に今年は複数案件の進捗重複等もあり気がついたら5月の暦になってしまっています。
この5月は父の命日であり、今から21年前の5月23日から目指す背中を失って、がむしゃらに櫓を漕いできたそのスタートの月であり、ときどきその軌跡を振り返るのもこの5月のタイミングであることが多いです。
今、その父は先祖代々受け継いできた八木家の墓所に眠っています。
21年前に父の遺骨を初めて納めて、安眠のときを過ごしてもらっていましたが、震災で傷が付いたものの御先祖様たちには、お客様の手直しが優先と我慢して、そのまま入っていていただいていました。
震災からしばらくたって仕事も落ち着いたということで、一昨年全面的に八木家墓地をリフォームしました。
先祖代々引き継いだ墓域は無駄に広くて掃除も大変なので、フラットな石貼り床に墓域の外柵を回し、本体はシンプルに和洋折衷型をデザインしました。
その右側には先祖歴代の霊標(戒名板・墓誌・法名碑とも言う)、左側には父がその両親(私にとっては祖父母)と、更にその両親(私にとっては曾祖父母)の略歴を記した碑銘板(略歴板・碑文)を配しました。
当然父の略歴は私が起案して石に刻むことになりましたが、あれもこれもと書くことをまとめられずに記載したところ、その後半に余白が無くなり(私?)の略歴を刻むスペースはほとんどありません。
まあ、それもいいかなと思いながら、5月の命日のお墓参りには毎年手を合わせに行っています。
そろそろ、NY視察感想のまとめをしようと思います。
前に書きましたが、NYの土地利用を見て、日本の土地行政や許認可をもう一度改めて考え直す必要性を感じました。
NYマンハッタンの面積は、東京の都心4区(千代田区・中央区・港区・新宿)の面積とほぼ同じ、或いはもっと比喩的に述べると山手線の中の面積とほぼ同じなのですが、そこにセントラルパークという日比谷公園の20倍もある緑地もある半面、ミッドタウンや証券取引所のあるビジネス地区などまさに摩天楼地区で、建物を建てる基準となる容積率は2,000%にもなる。ただ、歴史も大事にし古い建築物や証券取引所の1ブロック隣のトリニティ教会やその両側の古い墓地もそのまま共存している姿に、一律の規制や横並びの基準でなく、最大限の資源の活用を考えた基準があり、これを東京の規制に当てはめたら、空中活用や高度利用も随分と変わることと思いました。
日本の街作りはどこも同じ規制であり、どこに行ってもある一定の高さ制限や、使っているかどうかわからない形だけの公園整備など、まるで日本中同じ景色になりがちだが、密集地は密集の規約や規制、緑地帯はもっと大きなエリアでの判断など、街全体を俯瞰した視点が必要なのだろうと思います。
ついでに言えば、マンハッタンの街割りは京都や中国の西安のような碁盤の目の街作りだが、縦の道をアベニュー、横の道をストリートと区分し、ストリート間の移動は徒歩約1分(例えば52ストリートから51ストリートまで1分で移動できる)縦のアベニューは徒歩約3分(6番街から5番街までは約3分という意味)なので、ブロック角から全く反対のブロック角まで信号待ちを入れても約5分とツーリストにもわかり易く、徒歩でも簡単に目的地まで行けるし、また地下鉄も東京同様に路線が多くどこに行くにも簡単で、物価の高さを除けば本当に住みやすい町であると思いました。
居住者に優しい街は、旅行者にも優しい街になるのでしょう。
世界から憧れるNYはやはり行ってみてたくさん感じるものがありました。
追伸:訪問中は絶対ありえないだろうと思っていた、トランプ大統領の誕生で、通り過ぎただけのトランプタワーをもっとじっくり見て来れば良かったと反省しています。
でもニューヨークでは完全にヒラリー色が強かったんですけどね。
ニューヨークにはたくさんの美術館があり、芸術に関心のある人は、パリやロンドン或いはイタリアの有名な美術館巡りもいいでしょうが、一か所にまとまっていて同じ日に複数巡ることができるのは何といってもNYだと思います。
マンハッタンの中だけでも近代美術館、メトロポリタン美術館、グッゲンハイム美術館など集中して存在しています。
もちろんそれらの中には、絵画も彫刻も前衛芸術も混在していて、現代だけでなく古代の大理石彫刻までジャンル問わず展示しているのですが、今回はそれらも見た後で、石彫専門の美術館「イサム・ノグチ ミュージアム」にも行ってきました。
石の業界ではイサム・ノグチの石材彫刻は大変に有名で、その作品自体は今までも目にしていたり、彼が好きな石材である花崗岩や安山岩のことも知ってはいましたが、今回実際にその作品を見たり、その生涯を知って改めて感心するところがありました。
イサム・ノグチとあるので彼は日本人(日系1世)かとの印象がありましたが、実は彼のお父さんが日本人1世で、母親はアメリカ人であり、いわゆるハーフであったこと。
また、日本でも超有名になったのは、一時 女優で後に議員になった李香蘭(山口淑子)と結婚していたことも理由があったのかもしれません。
でもその頃にはすでに彫刻家、芸術家として実績を残し始めていた時でもあったので、今でいうロマンスやゴシップで有名になったというよりも、芸術の実力で人気を博していたのかもしれません。
いずれにしろ、今回のミュージアム見学は、石彫家イサム・ノグチの一生の中での石の扱い方や表現の仕方の歴史と変貌が感じられて参考になりました。
石の硬さを柔らかく表現したり、逆にその固さや自然観を強調したり、その感性に惹かれるものも多かったです。
石をピカピカに研磨する表現もあり、逆に自然のままの割肌や、粗い感じのノミ切り仕上げなど良く石を知っている人の奥深い表現が多用されています。
石はそのままでも石として存在しますが、人によってその石の意味合いや役割が変わってくるのは、まさに墓石でもそうであり、建築用の石材でもそうであると、改めて気づかされたような気がします。
結局、初めの疑問、アメリカの墓地に対する考え方は? についてのまとめをする必要があります。
今回紹介した野口英世のお墓、高峰譲吉のお墓、そしてマイルスデイビスらの数多くのミュージシャンのお墓はそれぞれ個性的で、その人物の人生を、生きた証を刻んだこの世に二つとない独自のユニークなものでした。
同じ墓地公園内には、石工事だけで数千万円はするだろうと思われる、宮殿のような霊廟もあれば、その隣にプレートだけのお墓がありそこに星条旗を捧げていたり、大きな樹の下にポツンと置かれたお墓など、全てがまるで自由に置かれているように見えます。
聞いたところでは墓地の使用料自体は日本とそれほど大差なく、夫婦二人用の墓域でおよそ50万円ほど。
そこに墓石をアレンジしたり、まだ土葬が80%のアメリカでは棺(ひつぎ)も重要なアイテムの一つですが、納棺や埋葬の費用をかけて死者を弔うこと自体は、国が違っても人種が違っても大きな違いはないと感じました。
ただ、自由の国アメリカ、そしてそこに住む人々にとっては、生きているうちも自由だし、死者にも同じく自由を与えていると思います。
日本の墓域はどちらかというと画一的で、寺院や霊園業者が大きさを決めてしまって、その大きさの中で眠ってもらうという、日本人の横並び性格が死んでからも色濃く残っています。
このウッドローン墓地は当然面積で使用料が変わりますが、家族用として大きな墓域をもらうこともできるし、一つの小さな丘を墓域として求めることもできるようです。(当然その金額は数億円とも数十億円ともいわれますが)
つまり、お金の有る無しも重要でしょうが、個人あるいはその死者の考えにより、大きなお墓でも小さなお墓でも皆が理解できる、共有できる状況なのではないかと思います。
現在日本はお墓離れが進んでいると業界では騒いでいますが、先祖に対する思いや、亡くなった身近な人への思いなど、横並びで一様に決まっているものではありません。
お墓を持たない人もいるだろうけど、出来るだけ良いものを作りたいと思う人もいれば、大きな形を望む人もいます。
ところが、区画の大きさはこれこれ、墓石の形はこれこれ、お参りの時間はいついつなど、画一化しすぎて死者や建てる人の個性や自由を奪ってしまっているのが日本なのか、今の問題なのか、とアメリカの墓地から見て思わずにはいられません。
また、埋葬の仕方が違うせいもありますが、この墓地では隣の墓域との境界があまりない、或いは気にならない、実際にはここからここまでという目印はあるのだと思いますが、それをまるで感じさせないおおらかさのような雰囲気があります。
あの世に行ってまで敷地や境界で悩む必要はないでしょうから、それも今回のカルチャーショックの一つでした。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.