



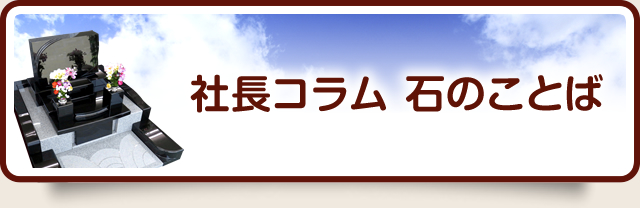
HOME > 社長コラム 石のことば
久しぶりに遠出をしてきました。
その辺りは昔よく行っていたり、知っていたりした場所ですが、11年前の東日本大震災で大きな被害を受け、街並みがすっかり変わってしまっており、復興まで10年の時を要しました。
新しい観光名所や、賑わいのある街並みも整備され、家族連れで行き来する人々の顔は、間違いなくあの時の苦悩から立ち直りつつあると確信しました。
ふと、その中に真新しい施設(建物)が目に入り、その裏手の駐車場に車を停めました。
建物付属設備を囲った場所の隣に、こちらは垣根を回した空間がひっそりと人目を忍ぶように存在していました。
その垣根の一か所だけわずかに開いていてそこから遠慮がちに出入りできるようになっています。
その中にモニュメントと碑が建っていました。
実は私はこれがここに在ることも知っていたし、このモニュメント制作に当社でも協力させていただきましたし、この会社のトップの方の工場立ち合いにもご一緒させていただきました。
ただ設置されて、現地での状況は初めて見せて貰いました。
モニュメントのお披露目というのは普通は目立つように派手に行うことが多いのですが、こちらはその意図から静かに目立たず被災者への哀悼や、生き残った仲間の誓いの気持ちを込めた、厳かで深い心映えのモニュメント制作と設置発表でした。
具体的な場所や事業所名は入れるわけにはいきませんが、仲間を失う哀しさとその遺族を思う心やりと、生き残った仲間の誓いの想いがこの碑に刻まれています。
モニュメントは碑とも言います。
碑は「いしぶみ=石の文」とも読みます。
別離した仲間にも後世にも、そして子孫や歴史に伝える石の文、想いを伝えるタイムカプセルが石碑なのでしょう。
この石碑を発注された、こちらの会社のトップの方の深くて思いやるのある眼差しの中、工場検査、製品検査をされた瞬間のお気持ちを考えると、今もズシリと心が悲鳴を上げそうになります。
この石碑は未来への手紙であるとともに、亡くなった仲間への慈しみ深い文であることを強く感じて帰途につきました。
ついにまつしまメモリーランドの社長コラム第200回目を載せる日が来ました。
2005年12月に当時のホームページ改修に合わせて企画された石のコラムを、ほんの軽い気持ちで担当しましたが、それから足掛け17年、月に1回位のペースでの投稿でしたので、その意味では漸く200回目に到達しました。
その間、途切れそうになったこともありましたが、拙い文章でも継続することが自分の使命であると思い、何とかここまで続けてこれました。
その原動力となったのは、その時々の読者の皆様からの励ましや応援もあったことで、正に感謝のしようもありません。
継続できたのは、読者の皆様のお陰であると改めて気づかされました。
どこかでどなたかが読んでくれている、何かの感想を抱いていてくれている、と思うとやはり大きなモチベーションになっています。
今回200回目に何を書いたらいいか迷っている時も、熱烈なある読者の方から第199回のコラムを読まれて、「そう言えば何でまつしまメモリーランドっていう店名(社名)なのか?」「初めて聞いた時に遊園地かと思った」「仙台には3つの遊園地があると勘違いしていた。(注:八木山ベニーランド、西仙台ハイランド(2006年完全閉園)、まつしまメモリーランド??)」「一つの社名に、まつしま(平仮名)メモリーランド(片仮名)中山店(漢字)の3種類の文字様式を使っているのは珍しいのでは」など疑問を解決する記事を書いたらどうか、という有難いアドバイスが寄せられました。
本当にそれでいいのでしょうか?
前回が「Landwork」の由来、今回は「まつしまメモリーランド」の由来???
もう、ではそのリクエスト(アンコール)にこたえる形にいたしましょう。
これで記念の200回のお話にさせていただきましょう。
時は遡って1998年頃、私が社長になって1~2年後の事です。
当時当社は建築バブルの絶頂期を過ぎて大理石等建築石材の頭打ち、売上減少の波がやってきており新規事業の必要性を感じつつ難しい舵取りを任せられた新米社長の混迷が続いていました。
そこへ山陽地区のある墓石卸会社の社長が、面識無いなか当社を訪問してくれました。
先方は墓石の卸先を増やしたい、新規の墓石卸の売上を増やしたいという事での営業訪問でした。その社長は同業の建築石材会社でも、なぜ当社の財務内容が良いのか、その内容なら新規投資力も十分あるだろうという下調べをしての訪問のようでした。
しかし以前もどこかで書きましたが、建築石材事業と墓石事業は全くの異業種で、扱う単位(cmと尺寸、平米と立米)も、お客様も、流通も、所属する業界団体すら全く違い一緒にやるなどとは考えたこともありませんでした。
一般の方から見れば、同じ「石屋」だろうと不思議がられますが、同業者で当社のように「建築石材」と「墓石」を同じように事業化しているところはほとんどありません。
今の話題の真っただ中に例えれば野球の大谷選手のピッチャーとバッターの二刀流と同じようなものです。
大谷選手と違うのは、最初から二刀流を自分の意思で進めたのではなく、始めは私も断ったくらいで、どちらか一つしか出来ない、メジャーの中ならその一つだって生き残るのが大変だ、くらいに思っていた平凡意識の新米経営者でした。
ところが、その社長は翌年再度当社に来社し、墓石の小売り立上げを手伝うから墓石小売り事業をやらないかと、強力に提案してきました。
その頃、新規事業として幅を拡げる方策が弱く、中国に事務所を作ったりはしたものの、大きく業績を改善できない状況だったこともあり、何度かの打ち合わせを経て当時の「松島産業の墓石小売り事業」を開始することにしました。
それから店舗土地の物色、建物の設計、小売りシステムの構築、担当人材の新規採用などなどいくつも山を越しましたが、最後に店名を決めるに当たって今回の謎説明となります。
松島産業墓石部?松島石材?まつしま墓石店?仙台石材?墓石のまつしま?・・・・
全てピンときません。(今でもそれらの名称にしなくて良かったと思います)
その時にその山陽の墓石卸会社では一部山陰地区等に墓石小売りのパイロット店として、あくまでも卸がメインの中、小売り事業として店舗名だけを「メモリーランド」という名前で展開していました。
「その名称良いなあ、それを使わせて。」
「特に問題無いです、どうぞ。」
と、大変簡単な話ですがそんな調子で「メモリーランド」は決まりました。
でも、突然仙台の泉区、4号線バイパス沿いに「メモリーランド」は何屋でどこの者?
やはり、当時の本体の松島産業という会社名からも取るべきとの考えもあり、小売りのお客様相手で軟らかさを求めて漢字の「松島」でなく「まつしま」を頭に持ってきました。
「泉店」は本当に希望だけでいつか2店舗3店舗と増えたら「まつしまメモリーランド」だけでは混乱すると思って泉店と入れたのですが、2年後に「長町南店」3年後に「北松島店」4年後に「中山店」となったのは自分でも信じられない幸運の集合でした。
そんな理由で「まつしま」「メモリーランド」「〇〇店」の合作となったのです。
最後に、その数年後、その時の山陽地区の卸会社の社長と再びお会いし、その社長方針で卸会社と小売り会社の会社分割を考えており、その小売部門の6店舗を譲り受けて「メモリーランド西日本」として当社のグループに迎えることになったのは、それからずっと後の事で2019年のお話でした。
まつしまメモリーランドの社長コラム「石のことば」も次回が記念の200回目となり、そこに載せる話題を何にすべきか今から悩んでいてなかなか構想が進みません。
また、そのプレ200回となるこの第199回も本当は何を書いていいのやら迷いに迷っていました。
いつもはこのコーナーに関してはその題名が示す通り、何らか「石」との関わりを中心に記載してきたつもりですが、今回は多少つまらないかもしれませんが、ランドワークという社名になった裏話をしていきたいと思います。
もともと当社の社名は松島産業株式会社(1965年7月1日設立)、私が入社したのは1984年ですから20年目に掛かる頃の事です。
その名称の由来は東北本線の松島駅前に在って、主力商材が松島石(野蒜石とも言われる凝灰岩)で、関連会社(先代代表の仲間と作った採掘加工の会社名は松島石材)の販売を一手に引き受けた形で、日本全国に販路を拡げたいという願いで産業株式会社と付けたらしいです。)
それから、当社は国産大理石、花崗岩へと扱いが拡がり、そして工場設備を有して外国産の大理石や建築石材など主力商品を拡げていきました。
2000年になって、墓石小売り事業を開始し(墓石卸売り事業はその前もやってはいました)その時の商標が「まつしまメモリーランド」です。
つまりちょっと大きな例えですが、あのユニクロが社名ではなくて商標であり、会社名としてはファーストリテイリングであるのと同様、知名度的にはまつしまメモリーランドの方が皆さんによく知られるようになりました。
その後、グループ多角化によって、不動産事業の品川倉庫建物、測量設計事業の一測設計、アイエスプランニング、オリエント測量設計、中国貿易輸出事業の大志貿易有限公司、事業組合の仙臺納骨堂と本体の松島産業を含めて7社になった2015年、ちょうど松島産業が設立50周年、品川倉庫建物が80周年、一測設計が40周年に当たる節目の時期が来ていました。
(今では、その後に墓石関連で秋田石材、やまと石材、まごころ価格ドットコム、山口石彫、メモリーランド西日本、石のヒラガと6社が増え、測量設計関連で佐藤測量設計が入り、そして本体からまつしまメモリーランドを独立させて、現状は15社の事業グループになっています。)
その2015年の50周年、80周年、40周年の合同周年イベントで、「松島産業グループ」というのは何か固い、古臭い感じがして、グループ名称だけでも作ろうかという流れになりました。
その当時は社名を変えるだけでも専門のコンサル会社があって、社名(この時はグループ名称)を考える専門家みたいな人たちがよく出入りしていました。
その専門家からいくつか提案をもらったのですが、今までにない言葉(造語)だったり、単にイニシャルを2つか3つ並べた社名だったり、ギリシャ語とかラテン語とか意味の分からない社名提案などで、これといったものが無く提案は全て却下でした。
でも、自分の奥深いところには、何か(当時は全7社)共通のシンボル的なものがあるはずだと、そんな漠然とした思いはありました。
「石材」(大理石・花崗岩)、「墓石」(墓地・納骨堂)、「不動産」(土地・建物)、「測量設計」(土地測量・道路設計)当社グループの事業領域を並べていくと、そこに共通するのは「土地・大地」であることが明確になり、そしてその「仕事」をして社会に貢献していく。
つまり「LAND」の「WORK」が当社グループのおおもとだと閃いて、この自分で出した案をほぼ強引にグループ名として採用しました。
ロゴやその空と水平線(地平線でもある)のイメージは流石に専門家の意見も加えましたが、その映像イメージの原風景も実はギリシャのサントリーニ島の水平線のイメージがありました。(写真②はそのイメージです。写真③は世界一奇麗と言われる同じくサントリーニ島イオの夕日の風景です。)
また、話を少し脱線させていつもの「石とワイン」の流れで話すと、ワインの違いを最も顕著に現すのはテロワール(土壌)と言われます。
ワインの良し悪しは、実はブドウや気候や醸造法も大きく影響しますが、絶対に真似が出来ないのはテロワールの違い、大地の違いがあのロマネコンティやシャトーマルゴーを産んでいることも実に興味深い「Landwork」なのですね。
さて話は戻って、2015年にグループ名称としたランドワークですが、2018年の12社に増えた時の経営体制発表会を機に、本体の「松島産業株式会社」を「ランドワーク株式会社」に、そして東京の「品川倉庫建物株式会社」を「株式会社ランドワーク不動産」に社名変更して、現在は名実ともに「Landwork」グループとして今に至っています。
これからもグループの変容はあるかもしれませんが、われわれは「Land」を「work」する基本を忘れないようにしていきたいと思います。
第200回目を前に多少堅苦しいお話にお付き合いいただきありがとうございました。
この2年間、全く海外には仕事上も個人的にも行けていません。
状況的にやむを得ないというのは理解できているのですが、やはり海外への憧憬は沸々と心の中で生き続いています。
特に仕事で最初に行ったのが欧州の中ではスペインだったこともあり、スペインの石材と共にスペインへの憧れは最も強いものです。
仕事上海外渡航回数で言ったら、グループ会社のある中国福建省は断トツ1位です。
次が20年以上前までの石材仕入れで韓国ソウルが2番に来て、欧州の大理石集積地イタリアのトスカーナ州が第3位となります。
スペインはその次に続く私の渡航記録上は第4位となります。
ただ、最初に記載した通り最初の取引がスペイン北部ビゴのピンクの花崗岩と東南地中海沿いのアリカンテのベージュ大理石を求めて訪問したのが強烈な思いとして残っています。
そして、何故かその取引のせいか誰かの推薦なのかははっきりわかりませんが、スペイン大使館を通じて南部アンダルシア州の石材視察、石材会社との商談のためとして、航空機チケット、宿泊費、移動費すべてアンダルシア州持ちで日本から5名ほど選ばれて招待されました。
アンダルシア州はスペインの中でも面積は2番目に広く、複数の有名な都市(コルドバ・セビリア・グラナダ・マラガ・・・)が多く、州の人口はスペインで1番です。
また、西はポルトガルと接し、南はアフリカ大陸モロッコとジブラルタル海峡で向かい合い、東は地中海に面した風光明媚、食材の多様さ、そしてアルハンブラ宮殿に代表されるイスラム教とキリスト教の攻伐合戦、同居融合など歴史的な多様性が土地に染み付いた素晴らしいところです。
ただ、スペイン全体の所得格差では、商業都市バルセロナや首都マドリッドと比較すると真逆の低所得、いわば貧しい地区であるのですがそれだけに人が純朴で、居心地のいい風景を与えてくれる地域です。
いま日本国内で一番目にするスペインの大理石は写真①ブラウン系の大理石かと思います。エンペラドール・オスクーロ(皇帝の濃色大理石?という意味になるかな)と思います。これは残念ながらここアンダルシア州の隣、アリカンテの近郊で産出されるのですが、以前のベージュ系大理石クレマ・マーフィルと合わせ大理石の双璧を成すものです。
参考までにスペインの地図とアンダルシア地区の有名都市を表示しておきます。(写真②)
そして最後の写真③はアンダルシア産の薄いピンク色の石材を使った、本当にどこでも目にするアンダルシアの豊かではなくとも心が温かい人々の暮らしを表出している中庭の風景です。
アンダルシアへの憧憬はこうして続いていくのでしょうね。
引き続いて出雲の話をしたいと思います。
やはり何といっても「いずも」と言ったら出雲大社を一番に思い起こすのは、食べ物好きもさることながら歴史好きのなせる業でしょうか。
平安時代の書に「口遊(くちすさみ)」というものがあり、そこに「雲太和二京三(うんた・わに・きょうさん)」と記載されているものがあります。
当時の建築物の高さの順番を書いたものと言われています。
雲太とは出雲大社の事でそれが一番、和二は奈良(大和)の東大寺大仏殿で二番、京三は京都平安京の太極殿とのことです。
出雲大社の高さは上古(伝説上の大昔)には32丈(約96メートル)、中古(この平安時代前後)は16丈(約48メートル)、そして今の世(江戸時代)は8丈(24メートル)だったと、国学者の本居宣長が本に残しています。
口遊に書かれた平安時代には、東大寺大仏殿の高さがおよそ45メートルだったとの確証があるので、それが第2位なら1位の出雲大社が48メートルというのは肯ける話です。
でも、当時そんなに高い建築物を建てることが可能だったのかと、長いこと疑問視されてきていましたが、近年西暦2000年になって中古の時代の出雲大社の柱跡が見つかり、その可能性が急に現実のものとなりました。
それは直径4~6メートルの円で掘り込んだ地面に礎石を置いてその上に3本の木の柱を金属の輪でまとめてそれを何10本も基礎となし、長い回廊階段の上に本殿を安置していたという事までわかり、復元模型も造られる事になりました。
それが現代になってわかったのも、礎石となって柱を支えた石材のおかげというのが、石という素材の恒久性ですね。
柱としての木材はいずれ朽ちてしまいますが、直接土に埋めてしまっては水分を吸い上げる為、木の耐用年数を長くする目的だった礎石が、柱が無くなってもそのまま歴史とともに残り、今に続く証言者になっています。
これだけの巨大な神殿で祖先を祀ったのも、他に類を見ない国譲りの歴史があり、太古の出雲族、出雲国は国内に於ける特別な存在だったのかもしれません。
出雲というキーワードで歴史好きの私には、もう一つだけ頭に浮かぶものがあり、最後に記載します。
「出雲阿国」
そしてその阿国の墓と伝えられる墓所です。
なんと、その外柵(お墓の周りの外構)はあの来待石(出雲石)のように見えます。
やはり歴史と石はつながります。
最近、仕事で山陰に行く機会が多くなっていました。
山陰への入り方は電車の場合は岡山から「やくも」という特急があり、新幹線を乗り継いでやくもで行く方法もありますし、広島側からシャトルバスで松江方面に入る方法もあります。
しかしながらどちらも、かなり時間がかかるので基本的には飛行機を利用しています。
山陰の空港は鳥取空港、米子空港、石見空港と結構利便性はあるのですが、もう一つ(マイナー?)な空港ですが、出雲大社観光には最適な出雲空港があります。
出雲というとやっぱり出雲大社が誰でも思い浮かべる第1位と思いますが、その他にも出雲そばや宍道湖のシジミ、しまね和牛など全国的にも有名な物品も多くあります。
そんな出雲ですが、石屋の職歴が長い私は、出雲軟石を思い起こしてしまいます。
正式な名称は松江市宍道町周辺で採れる「凝灰質砂岩」の来待石(きまちいし)です。
こちらは面白い来歴の石で、本来は火山岩系の柔らかい凝灰岩が基になっていますが、その火山灰がそのまま固まらず(そのまま固まると凝灰岩)浅い海の中に堆積して砂と一緒に固まったものです。
それ故に非常に柔らかく、加工がし易いことから、出雲大社の大昔から古墳の中の石棺を作ったり様々な石像なども加工されてきていました。
どれだけ柔らかいかというと、その採掘場(丁場)の写真を見ると一目瞭然、大型の機械が無い時代でもこんなに真直ぐに丁場を掘り進むことができるのは、まるで豆腐を切るような感じで採掘できた証です。
近年には灯篭や庭園用の石、寺社用の狛犬など細工の楽さ(硬い御影石と比較しての事ですが)で日本全国に供給していた時代がありました。
私も業界に入った40年近く前に、当社が「建築石材」「墓石」と「造園石材」の3本柱で業務を行っていた関係で、その来待石の灯篭=出雲灯篭の形と名称を必死に覚えた思い出があります。
今でも記憶だけで「春日灯篭」「雪見灯篭」「利休型」「みよし型」と形も名前も出てきますし、「織部灯篭」「岬灯篭」などの変わり種も覚えています。
同様に「猫足」や「蹲(つくばい)」など、やはり若いころに覚えた記憶って、しばらく使っていなくて脳の中で、火山灰のように積み重なっていても、ひょんな地殻変動で掘り出されると、はっきりした形で蘇ってくるものなのでしょうね。
ここ数年初詣に行ったかと聞かれたなら、所謂元旦とか1月2日とかの本当の意味での初詣参りは、タイミング的に行けていないのかもしれないですが、やはり年末年始のタイミングでの「初詣代わり」として年末の神社とか年明けの神社とかに参詣することはよくあったように思います。
風物詩になってしまっている、年越しから新年あけての初詣や、本来は1月2日と言われている神社への初詣もなかなかタイミング的に合わずに行きそびれていた昨今かなと反省しているところです。
ただやはり年始に神社のお参りっていうのは、何か日本人としては心も潔くなり、結果的に1年の中で一番神社に行ってしまうのは1月が多かったかもしれません。
そして神社と言えば何故か石がありますね。
最近の流れでは流行のデザイン看板を上げてその神社の由来を上げるよりも、やはり御影石に由来や縁起を記入し、歴史的な味を含んでちゃんと見てもらう工夫をしています。(グレー系の御影石には彫った文字が目立たなくなるので黒い塗料でくっきりと文字を目立たせます)
でも、もっと古くて地方や各地元の神社では、必ずと言っていいほどその由来を記した大きな石碑(大抵は硬くて文字を彫り難い花崗岩ではなく、地元の安山岩や玄武岩・粘板岩が文字彫刻が容易く結構多いです)があり、旧漢字や用法や多少の読み難さも相まって解読は難しいですが、それこそ歴史を感じることができます。
そういう意味で、石は神社という歴史遺産の中の一つの構成物であり必要なピースであるともいえるでしょう。
まあ、そんな中、新しい神社参詣者の多数を占める若い女性向きに、写真3のようなもともとあった自然石(庭石のような単体の置石)を、効能込めてパワーストーンの先駆けとする流れも石と神社の関係であってしかるべきと思い、それはそれ初詣の御利益や時代の流れの中で良しとしたいものですね。
毎年年末になると、「今年の漢字1文字は?」でよく盛り上がります。
確か昨年は「密」今年は「金」だったかと思います。
以前のコラムで弊社のロゴになっている「磊」についてアップしたところ、意外にも反応が良くその流れで石偏の漢字を探してみました。
思ったよりも石偏の漢字って多い割に、普通には使っていないものが多くて「磊」同様に意味も読み方もなじみが薄いものが多いです。
もちろん石に関係のあるポピュラーな漢字もたくさんあります。
研、硬、砂、砕、碑、磨、礎、砥、、、、などは石屋でなくても普段から目にし、分類では後者になると思います。
ところが、なじみの薄い前者の漢字の例としては、矼、硲、砒、砺、砿、、、などなど、読みがわからないものも多くありました。
特に今回見つけた漢字の中では「砅」、これって何?という感想です。
また一般の辞書では出てこないものに、上の漢字は石の右に水で1文字ですが、石の下に水で1文字のものも別にありました。
この漢字を見て、石屋として思い出すのが、ウオータージェットマシーン、ウオータージェット加工というものです。
これは弊社工場に2台のマシーンがあって、常にフル稼働しているものですが、要は石を水で切断する機械です。
通常は工業用のダイヤモンドが先端に付いた丸い刃物でカットしていくんですが、それだと直線は切れても、円形やギザギザの線で切っていくのは出来ません。
特に使われる加工としては1枚物の石材の中に丸い穴をあけて器具を取り付ける洗面台加工やシンクの加工で重宝します。
また特殊用途としては、石材のモザイク使用、床や壁に違う石を使って絵やデザインを作っていく加工にはこれが無いと出来ません。
昔弊社で扱った超有名なテーマパーク内にあるホテルの工事では、全てのエントランス、エレベータホールの大理石モザイク床の加工で、このウオータージェット加工機を休み無しにフル操業させた思い出があります。
まさに石を水で切る、砅の漢字の具現化です。
皆さんにも分かるようにウオータージェット加工の写真を載せます。
ちなみにこの「砅」は「レイ」「ヒョウ」「わたる」と読むそうです。
尚、最後にこのウオータージェットのイメージはもう一つの漢字も引き出します。
石に高圧の水が勢いよく流れていく様で、「硫」という漢字でもいいかもしれません。
こちらは意外と「硫酸」という時に使うので、先の分類からすると、読めない石偏とよく知っている石偏の中間の漢字でしょうか。
昨年、日本全国47都道府県の最後の訪問県である高知県を訪れたことにより、全国すべて行ってきたような気持ちでいましたが、なんと今回初の隠岐国(昔はここも単独の行政区)へ行く事になり、自分自身まだまだ未踏の地が多いことに思い至りました。
そういう意味では佐渡島や淡路島を除けば、壱岐島や対馬島にもまだ行く機会がなく、それぞれ昔の壱岐国だったり対馬国だったりしたので、離島に関してはまだまだ行けてないところが多いです。
今回は、グループ会社の仕事での訪問で、滞在時間はわずか数時間でしたが、のんびりと観光なども出来ればよかったと思います。
なかなか隠岐の事を知る機会もなかったのですが、改めて調べると大きく島は四つあって、前(本土側)の三つの島(知夫里島、西ノ島、中之島)を島前、奥の一番大きな島(隠岐の島)を島後と言い前後に呼び分けています。
それぞれに行政区が違い、地夫里島は知夫村、西ノ島は西ノ島町、中之島は海士町、隠岐の島は隠岐の島町(旧西郷町)と言うようです。
人口は島前島後の4島全部でも19,000人余り、漁業と観光で成り立っている町です。
実は行く前から多少は土地勘は持っていました。
司馬遼太郎が亡くなって、歴史ものの新刊を読めなくなって久しい時に、知人から紹介された飯嶋和一という人の歴史小説が面白く、この隠岐の島後を舞台にした「狗賓童子の島」という小説で隠岐の島の地図と一緒に話を進めていく読み方で、大体の感じは持っていました。
また、何といっても流刑の島としての印象も強くここで生涯を終えた後鳥羽上皇や、或いはここから脱出してその後さらに活躍した後醍醐天皇など隠岐は歴史とともに存在してきたと感じています。
更には、石屋としてはこの島から産出される黒曜石の事も紹介する必要があるかと思います。
黒曜石というのはガラス質の多い火山岩で、色はほとんど黒色のため黒に耀(ガラスで輝いているため)の字で本来は黒耀石と言いますが、今は曜日の曜で黒曜石でも通ります。
ガラス質であることから、脆さはありますが割った断面は切れ味のいいナイフや剃刀のようで、石器時代から手斧や矢じりの材料とされてきました。
そして、このための良質な産地は日本国中でも数カ所しか存在せず、全国でも北海道、栃木県、長野県霧ケ峰周辺と並んでこの隠岐の島の黒曜石は良質なため盛んにほかの地域から求められました。
面白いことに同じ黒曜石でもその成分分析をすると、どこの産地のものがどこまで流通していたか、発掘された石器を調べるとわかるようでその検証もなされています。
また、この石は世界中いろんなところで同質のものがあり、世界史的には石器時代ばかりか、青銅や鉄器文明を経ずに、南アメリカのアステカ文明などは15世紀までこの黒曜石が最高の武具として存在していたということです。
隠岐の黒曜石は、山陰地方はもとより、山陽地区、近畿地方、一部四国や北陸まで渡っていたというのでこれも面白い研究だと思います。
隠岐は本土から流されてくるだけでなく、本土へ輸出して広めたものもあるという事実にもう一度振り返ってみることも必要かもしれないですね。
お客様から当社への質問で今でも多いのが、看板やロゴマークになっている「磊」の文字を何て読むのか教えて、というものです。
実はこの漢字、ちゃんと辞書にも載っていますが、用語として使われることが非常に稀で、確かに馴染みが薄い漢字ではあるのかなと思っています。
私が知っている用語としては、四文字熟語の「豪放磊落(ごうほうらいらく)」くらいなもので、あとは宮城県仙台市民限定で、仙台市秋保温泉渓谷に存在する「磊々峡(らいらいきょう)」というのがあって聞いたことがあるというくらいかもしれません。
他に色々調べると「磊磊落落(らいらいらくらく)」や「不羈磊落(ふきらいらく)」等同じような意味の熟語があるようですが、基本的には心が大きく、おおらかで、細かいことにこだわらないさまを言うようです。
つまりその質問の答えとなりますが、「磊」は「らい」と読み、意味は「心の広いさま」を表していますが、もう一つ漢字の成り立ちから「石が積み重なっているさま、石がごろごろしているさま」という意味もあります。
ちょうど、「豪放磊落」などの四文字熟語は「心の広いさま」の意味に対して、「磊々峡」の方は「石が積み重なっているさま」の方の後の意味となります。
「まつしまメモリーランド」やグループ各社の石材関連会社で使用しているロゴの「磊」は当然ながら後者の意味を表しているとともに、ロゴ作成時の理念として「1・建築の石材、2・お墓の石材、3・造園や環境の石材」の全域を取り扱える石材会社としてのオールマイティさと、「代々積み重なる石(故人)の記憶」を表すシンボルの意味も込めました。
確かに珍しい漢字で読める人は少ないですが、もともとの中国では普通に目にする文字で、ちょうど「木」と「林」と「森」や「日」と「昌」と「晶」の関係のように、日本でもよく浸透している重ね文字と、こちらではあまり見ない「金」の3つ重ねや「火」の3つ重ね、「人」の3つ重ねの漢字などよりは未だ馴染みがあるのかなと自分では、ポピュラーな方の漢字なのかなとは思っています。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.