



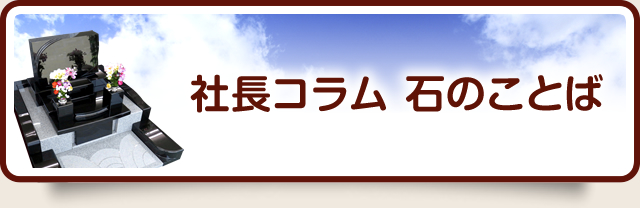
HOME > 社長コラム 石のことば
中国の南部、福建省の中央地区に泉州市が在ります。
その泉州市の管轄下に恵安県(中国は市と県が逆の立場です)があり、更にその恵安県の行政下に崇武鎮(村と言うよりは町か市くらいの大きさですが)という所があり、石材工場が約300軒集中しています。
我われ石屋さんは、石材加工の確認の為にこの崇武鎮をよく訪問します。
当社の100%子会社 大志貿易が在る福建省アモイ市からは高速道路で約2時間、最近開通した新幹線を利用しても駅からの車利用と合わせ同じく2時間ほどの所にあります。
以前から、何故この崇武にそんなに石屋が集中したのか、なぜ世界的にも大きな石材産地を形成したのか疑問には感じていました。
今回、いつものように石材加工の確認を終えて、天気も良かったので船から崇武を眺める機会を持ちました。
この辺りは昔から海運業が盛んで、各地との交流が盛んだったところです。
それだけに、海からやってくる外夷の恐怖もあったのだと思います
写真1は海からでなければ見られない、崇武古城の突端付近です。
まるで万里の長城のように、石の擁壁が続き、突端に巨大な灯台と周りにはたくさんの守護像が立っています。
もちろん近くに白御影石の丁場(採掘所)があることも要因ですが、このような巨大造作技術を必要とされる場所だった為に、ますます石加工の技術が集積していったものと思います。
そう言えば日本の石材産地も城郭石垣技術から進んでいった地区が非常に多いです。
そんな巨大加工技術とともに、写真2は食べ物の見本(メニュー見本)を全て、石で作ったのが飾られていました。こちらはとても細かい技術です。ホテル内のレストランへと続くロビーにありました。
最後の写真は、その崇武鎮で最も新しい、(自称?)5つ星のホテル正面です。
10年前は村の民宿を少し良くした程度のホテルしかなかったのですが、先月ここを見てまたしても中国の成長の早さに驚いてきました。
「知床の岬に ハマナスの咲く頃 思いだしておくれ 俺たちのことを
飲んで騒いで 丘に登れば 遥かクナシリに 白夜は明ける」
何度となく北海道には行きましたが、今まで知床半島に足を踏み入れたことがありませんでした。
今回、超過密スケジュールでしたが、念願の知床世界遺産を見てきました。
有名な阿寒湖、摩周湖の更に先(東側)、知床半島のほぼ中央に、ウトロと言う場所があって、そこから知床の岬を巡る知床遊覧船が出ています。
おーろら号と言う遊覧船の発着広場に写真の森繁久弥歌碑が建っていました。
冬には流氷が漂着し、一面の氷の海を見せてくれるそうですが、この日は内地に劣らぬ真夏の日差しで、水が恋しく海岸に下りてみました。
何か今まで見た海岸風景と違う違和感。
海岸に降り立って足の感触で分りました。
砂の海岸でなく、砂利の海岸、特に全て玉石が続く海岸線です。
まるで川や河口で見られる丸い石が延々と続いています。
(そのまま、「知床砂利石」と銘打って販売出来そうな・・・なんて不埒な事は考えていませんが。)
これは近くの花崗岩層が海に崩れて、よほどの荒波に揉まれて丸くなったものか、或いは、遠くロシアの川岸から流氷に乗って流れ着いたものか、いずれにしろ全部が丸い玉石海岸でした。
最後の写真は世界遺産 知床五湖に映った羅臼岳です。
「別れの日は来た ラウスの村にも 君は出て行く 峠を越えて
忘れちゃ嫌だよ 気まぐれカラスさん 私を泣かすな 白いカモメよ」
本当にあっという間のお別れでしたが、北海道の広さを実感した旅程でした。
ストーンサークルと言うと有名なのがイギリスのストーンヘンジなど日本以外の太古の遺跡を思い浮かべますが、日本にも多くのストーンサークルがあるのを最近知りました。
観光を兼ねて夏の八甲田山系に登った帰りに(もちろん車とロープウエイが中心で歩きはほんの少々です)、秋田県の十和田インターのすぐ近くにある大湯環状列石に偶然立ち寄りました。
今から約4,000年前縄文時代後期の遺跡で、万座と野中堂2ヶ所の環状列石群が見つかり、復元展示されていました。
その目的や使用など細かいところは解明されていませんが、平均で1個30 、最大のものは200 の物もありその数は全部で7,200個が見つかっています。
今風に言えば総重量216トン、20トントレーラーで運んでも11台、4トン車では54台分を、約6 離れた安久谷川から人力で運んだエネルギーを思うと、彼らにとっては何かとても大きな意味があったはずです。
またその石群は全て同一石種で、閃緑岩系の玉石で、青緑みかげ石です。
この川からは、白色の花崗岩系石材や黒色の安山岩系石材も有った筈ですが、この綺麗な石だけにこだわったようです。
一部にはその石の下から人骨が発見され、お墓として使われていましたし、特に性別、年齢、地位などの違いで何種類かの集合墓があった可能性もあるようで、まさに当時の人々の死生観、死者への弔い、先祖供養(まだ仏教思想は生まれていませんが)など普遍の行動が伺えます。
また、祭祀に使われたであろう遺跡や、太陽信仰としての日時計型配石もあり、その中心から見ると夏至の太陽の沈む方向と一致しているそうです。
古代の人々のパワーが石に宿ったまま、4千年の時を経てきている現実にしばし圧倒された大湯環状列石遺跡見学のいっときでした。
もう少しで35℃以上の猛暑日となる一歩手前、都内で34℃を記録したその日に、初めて高尾山に登りました。
山頂までの道すがらあまりの人の多さにびっくりしました。
それはまるで駅前の商店街か、人気テーマパークさながらの人の流れでした。
聞いてはいましたがまさに高尾山ブームです。
しかしながらこれは今いっときの事だけでなく、遠く何百年にも亘って多くの人々から愛され畏敬されてきた信仰の対象でもあります。
それはいたる所に石碑・石像・奉納石として現代の人々に伝えられています。
どうしても石屋の目で見てしまい、これは秩父の青石かな、これは神奈川の小松石、こちらは伊豆の六方石かと石の来歴や由来を辿りながらの登山でした。
中には仙台石といわれる石巻産の石材や岡山県の万成と言う石もあり、本当に日本中から信仰寄進の為に集められ、そしてこの急な勾配を人力で運んできたことを思うと、何か琴線に触れるものがありました。
更には開山者を祀る祠と石像はやはり中国の石でした。
写真はありませんが引っ張り蛸の赤い石像はインド産です。
日本だけでなく世界中から石材を運び、この高尾山の登山道に設置奉納されたことになります。
そんな中、現代の奉納風景の一つに企業の寄進や広告を兼ねた階段石もありました。
参考までに紹介しておきます。
マカオの石の話をもう少ししていきます。
マカオでは最も有名な観光地で壁だけが残って立っている聖ポール天主堂跡、この周辺はマカオの旧い街並みの中心地に近く、たくさんの教会や市庁舎など歴史的な建造物が多いエリアです。それらの石の多くが母国ポルトガル産であることに驚かされます。
言ってみれば帆船や蒸気船で石が運ばれてきてここに現存している風景です。
そして2番目の写真は、ベネチアン・マカオ・リゾートホテルの世界最大級の広さを持つカジノの中二階です。(カジノの中は当然ながら写真撮影禁止のため分かりにくいかと思いますが。)
ここは客室が何と3千室、それも全てスイートタイプの部屋です。当然これも世界最大を誇ります。
ここのエントランス、ロビー、ホール、廊下、外壁など全ての共用部には本物のヨーロッパ産大理石がこれでもかと言わんばかりに使われています。まさに石に埋まるばかりの使い方をしています。
これらの大理石はコンテナ船や航空貨物として運ばれてきたものでしょう。
近年の石産業がもたらした風景です。
さて、3番目の写真は外の景色ではありません。
そのホテルの3階にあるイタリアのベネチアをイメージした室内の建物です。
この近くには実際に大運河(カナル)もあり、ゴンドラも就航しています。
しかも何とその運河が3ヶ所も巨大ホテルの3階部分に存在しています。
ここの素材は一部に本物の石を使っていますが、重量的な関係もあり石モドキの人工素材が混在しています。質感は全く違うものの遠目では本物の石のように見える技術です。
ここは過去と現在と未来を融合したような、ちょうどディズニーのテーマパークのような風景です。
石景色を中心にマカオの風景を考えると、歴史と豪華さとアミューズメントの入り混じった、そしてアジアとヨーロッパとアメリカの混在した、奥深い魅力のある所だと思います。
文化のあるところに石は集まる、とイタリアの先輩社長がよく言っていましたが、まさにその良き例だと感心しました。
先日、研修で香港・マカオに行って来ました。
香港は仕事で行くことも多く、また中国アモイへのトランジットで使ったりと最近の変化はよく見ている方ですが、マカオにはなかなか用事も無く、平成3年(1991年)の社員慰安旅行で行ったきり実に19年振りの訪問でした。
19年前にはいずれも出来ていなかった、バンジージャンプで有名になったマカオタワー、島と島を結ぶ自動車専用道路、そして今や本場ラスベガスに並ぶ超豪華なホテル群と巨大カジノ、まさにここはいったい何処?状態でした。
ただその中で、旧いものも大切にされ世界遺産登録31箇所は世界第3位、昔と変わらぬ景色も至るところに残っています。
マカオの歴史を見ると約450年前にポルトガルが租借し、以来本国ポルトガルの首都リスボンを真似た街造りをしてきた過去があります。
同じようにイギリスが租借した香港はまだ150年の歴史しかなく、そのような意味では同じく異国情緒漂う街並みでもポルトガル風とイギリス風、そして450年と150年の違いをはっきり表しています。
マカオの石畳はヨーロッパを思わせるものが多く、当然ながらその石の材料自体もポルトガルやイタリアから運んできたものです。
その石畳、或いは石の広場には、風景にピッタリ合う石の置物、石のプランター、石の柱が気取る事無く普通にたたずんでいます。
まさに生活の中の石の使い方が生き残っている街並み、そして石景色です。
今春オープンしたストーンライフのコンセプトがそのままここにあります。
石を通して豊かな心や余裕のある生活を提案していければ良いと思っています。
19年ぶりのマカオは雨の出迎えでしたが、雨に濡れた石畳もまた風情があって、とても印象に残る訪問でした。
前回コラムでお伝えしたストーンライフのピザ石窯がお陰さまで大変好調です。
家庭や生活シーンでの石の使用がなかなか前例が無かっただけに、やってみるまではとても心配していましたが、こんなにも興味関心を持っていただけるとはある意味予想外でした。
景気悪化や世情不安、生活不安等の悩みを抱えつつも、人はどこかに心の余裕や人生を豊かに生きたいとの願望を持っています。
そんな願望を手近に叶えてくれるものには、家族や親しい仲間と楽しいひと時を過ごす事や、お金をかけずに豊かな時を過ごす事があります。そんなシチュエーションにピッタリなのが庭の石窯や石のテーブルなのでしょう。
ご来場者には若いカップルから小さなお子様が居るいわゆるニューファミリー、シニアのご夫婦、またはお祖父さんお祖母さん以下三世代の大家族など、あらゆる年代の方々に亘っております。
そのようなお客様からの要望も多く、ピザ窯研修を兼ねたピザ焼き実演を不定期ですが行っております。
そのせいか、スタッフの中にはピザ焼きの技術がどんどん上がっている者が居り、石屋で失業してもレストランをやれそうな雰囲気です(笑い)。
彼らの言では「イタリア産の小麦粉の場合は合わせる水も硬度の高いイタリアの水が合います。」とか「トッピングに使うアンチョビは塩分が多いので厚焼きの方が良いです。」とかまるで〔ピザハウス・ストーンライフ〕のシェフのようです。
来月には社内の親睦会でもピザ焼きツアーが企画されたため、2人のシェフは今から大張きりです。(実施後にまたコラムでご報告したいと思います。)
尚、ストーンライフ山形専用のホームページを企画中ですが、より良いものをご提供したいといろいろ校正を重ねておりまして、アップが遅れており申し訳ありません。
ホームページでのご注文も、現地で展示品を見てのご注文と同じように出来るように作成中です。近日中乞うご期待!
昨日4月29日(祝)に新業態の店舗を開店致しました。
ここは先月3月27日(土)にオープンした、まつしまメモリーランド天童店と同敷地内ですが、建物も別、展示スペースも別、スタッフも別、展示品や取り扱い品も違い、ロゴマークや店舗名も全く違う「ストーンライフ山形」の誕生です。
何を取り扱っているのかと申しますと、ロゴマークの色に意味付けがなされていますが、赤・緑・水色・グレーの4色で磊の字を表したロゴがそれぞれ、赤とグレー(火と石…ピザ石窯やバーべキューコンロ)、緑とグレー(植物と石…石プランターや造園石工事)、水色とグレー(水と石…露天石風呂や水鉢)を意味し、そして取り扱いの商品を表現しています。
具体的には外部にモデルガーデン展示場が数種類常設されており、また石のベンチやテーブル、遊具なども展示しております。
また内部のショールーム内にもピザ窯のタイプ別展示や石彫刻品、癒しの石製品など提案型の室内展示場となっております。
当社スタートがビルやマンション等建物に使う『建築石材』、その後始めたのがお墓を扱う『墓石石材』、そして今度は一般生活の中の、言わば『生活石材』とでも云うべきジャンル(生活石材と云う言葉や分類は無いので、勝手に考えて命名しました)の業種であり、これで『石屋』の3兄弟(建築石材の松島産業、墓石のまつしまメモリーランド、生活石材のストーンライフ)が揃った記念すべき誕生日となりました。
昨日は空模様が今ひとつで、正午頃の大事な時間帯には雨が降り風も出たり、朝と夕方にはお日様も見えたりと安定しませんでしたが、会場は石窯ピザの実演・試食イベントもあり予想以上のお客様にご来店いただきました。
あまりの好調さに3時前にはピザ生地も底を尽きてしまいました。また昨日だけの実演販売予定も多くのリクエストから急遽ゴールデンウィーク中の5月3日と4日の2日間特別石窯ピザ実演会を開催することになるほどの盛況でした。
改めて関係した多くの皆様に感謝いたします。
ありがとうございます。
「生活石材 ストーンライフ山形」を今後とも宜しくお願いいたします。
(ホームページ等の修正がまだ間に合っていませんが、追加修正手配中です。)
おかげさまをもちまして先月末(3月27日)山形県2店舗目の「まつしまメモリーランド天童店」をオープンさせていただきました。
昨年12月20日に出店を決定してから、大幅改装やスタッフの異動・教育など短期間でのオープン準備で、数々の問題点をクリアしながら無我夢中で走るのはいつもと同じであり、担当スタッフをはじめ後方応援の部門や直接関連は無くとも全社応援があっての事で、また協力頂いた外部の方々や業者の皆様のおかげと、感謝の念でいっぱいです。
前から持論として思っていることですが、問題点が全く無いようにして完璧に物事を進めて行くことは、本当ならとても素晴らしいのですが、得てしてそのような場合はスピード感が無くなり、時間の概念が飛んでしまうことがあります。
百点満点を意識しすぎると同じ場所で足踏みをしてしまい前に進めなくなる、それなら六十点七十点でも良いから常に前に駒を進め、短期間に集中して完了させてしまう。
問題があれば立ち止まらずに前に進めながら解決していく、そんな進め方を今までも実行してきました。
以前ある新聞社からの取材に「拙速は巧遅に勝る」を信条としています、と答えたことがありましたが、百点取れない言い訳も多少有るにせよ、このような進め方は性格なのかもしれません。
ところで話は変わりますが、その天童店において、1号店の山形店でも店のキャラクターとしてフクロウの石の彫刻を飾りましたが、今回は更にバージョンアップして、フクロウ彫刻をたくさん展示しています。
フクロウは古来より縁起の良い鳥として漢字では「福籠」とか「不苦労」とか書かれており、とても御利益がありそうな字面です。
天童店のマスコット、店のイメージキャラクターとして皆さんに認知していただけたらと思っております。
先日最近話題の3D映画「アバター」を観てきました。
ご覧になった人も多いと思うので、ここでは話の内容については省略しますが、本当に技術の進歩には驚かせられるばかりです。
3D映画と言うと、昔の学習雑誌の付録についてきた青と赤のセロファンのメガネをかけてぼんやりした映像を見る感じや、良くてテーマパークの中で恐竜などが異様に近づいてくる映像に視神経が酔ったような状態になったりと、あまり良い印象は無かったのも事実でした。
しかしながら、今回の映像は本当に奥行きがあり、立体的でリアリティーがあり自分自身が中に入っているかの錯覚さえ覚えます。
しかもそれが極めて自然で、途中で退席した観客がスクリーンに影を作って出て行ったのでなく、シーンの中を通って出て行ったような気になりました。
視覚差による脳の酔い状態もそれ程強烈でなく、ましてや元々メガネをかけている人用に、オプションでクリップ式のサングラス型もあり、最後まで違和感を感じないまま見ることができます。
映像の中に出てくる、ストーリーの核となる鉱石や磁力を帯びた岩など、石屋としても本物の質感に驚くばかりでしたが、何か一つ足りないもの、目では匂いとか温度とかは当然伝わりませんが、もう一つ伝わらない大事なものが気になりました。
それは重量感とでも言えばいいのでしょうか、なぜか重さを感じ無かったのが不思議でした。(宇宙空間で重力が少ない設定や、磁力で浮く岩のせいでなく、石本来の重さが意識できなかったのです)
石屋だからかもしれませんが、普段は石を目で見ると同時にそのものの重さが無意識で感じるものなのですが、今回の3D映像には立体感、質感、リアル感など本物と全く同じように脳が受け止めているにもかかわらず、重さを意識できない、重量感が感じられない。
そういえば、石屋のCADにも3次元表記の完成予想図面(3Dキャド図)があり、お客様に見ていただいてから工事に入るようにしているのですが、そのキャド図も立体的で、石の色目も良く出ているのですが、やっぱり重さを感じない、石としての迫力が無い。
「石」の本物と「3D」の映像の最後の違いが重量感だというのは、常に重い石を取り扱っている石屋だから思うことなのでしょうか?
とても不思議です。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.