



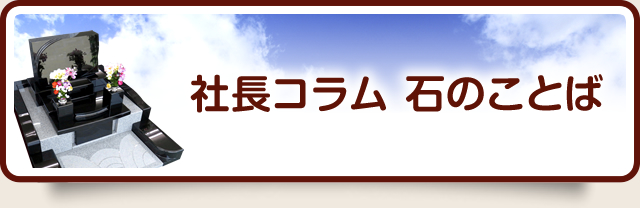
HOME > 社長コラム 石のことば
まつしまメモリーランド 八木社長様
紅葉の落ち葉も、間もなく雪のおしろいを付ける季節となりました。
八木社長様、ご無沙汰しておりますがその後いかがお過ごしでいらっしゃいますか?
きっと日々忙しく国内外を駆け回っていることと思います・・・・。
この度はご縁があって御社にお世話になり、心より感謝しております。
オープンしたばかりだった山形店に初めてお邪魔したのは、まだ残暑の厳しい季節でした。私には初めての経験で、お墓に関する予備知識も全く無く、不安を胸にそのドアを開けたのを鮮明に記憶しております。
でも、そんな無謀な私に対して、社長を始め、まつしまメモリーランドの社員の皆様は心温かく迎えて下さいました。その第一印象が再度訪問する決め手となり、二度目の訪問の時には、ここでお世話になることを心の中で確信しておりました。
わからない事を質問しても、丁寧に解りやすく笑顔で答えてくれた佐々木さん・・・。
私の二人の娘たちに、わざわざ自宅から使わなくなったおもちゃを持ってきて遊んでくれて、夢中で商談する私を助けてくれた鈴木さん・・・。(子供たちは今でも、”まつしまキッズランド”へ連れてって!!とせがみます)
どんな時でも誠心誠意を込めて対応し、常に安心感と信頼感を与え続けてくれて、まるで顧客としてではなく、一人の人間としてお付き合いしてくださった矢口さん・・・。(母が亡くなった際にはわざわざ自宅へ足を運んで下さり、励ましのお言葉をかけてくださいました)
そんな皆様に支えられた私は本当に幸せです。
そして、社長はこれ程までに素晴らしい社員をお育てになられたのですね。八木社長は寛大でいて、その風格を誇張することなくやさしさに溢れ、その姿勢と生き方・考え方は私の心を掴んで止みません。山形のコミュニティ新聞に掲載された社長の記事を読んでそう思いました。私も小さな会社の一役員として社員を育てることの難しさを日々痛感しているからです。
注文から完成までの一貫したシステム、ミスを犯さない為の仕組み、入念な打ち合わせや予定表・・・。まつしまメモリーランドのコーディネイトは見事でした。私はそこから自分の仕事に学ぶべきものを得たような気がします。
そして完成したお墓を目の前にした時には、決して大きくはないのに壮大で、堂々と誇らしげに聳え立つその姿に感動しました。一際光り輝く我が家のお墓に住職からも「大変立派なお墓ですね。丸みを帯びた部分がやっしさを感じさせる。ご両親の憩いの場所となるでしょうね」とのお言葉も頂きました。
『憩』という竿石に刻んだ文字については、矢口さんにいろいろ相談し、アドバイスを受けながらようやく決まった想いのつまった文字でした。
まるで亡くなった父と母が「こんなにステキなお墓を建ててくれて有難う」と言ってるかのように、私には聞こえます。
私は「そうなんだよ!まつしまメモリーランドという素晴らしいパーフェクト集団と出逢ったんだよ」と返事をかえしました。
私は、これまでいろんな買い物をしてきて、これ程までに満足度120%を感じたのは初めてでしょう。そしてどんなことにも、人と人との信頼に勝るものは無いことを学ばせて頂きました。出逢えた事に感謝しております。本当に有難うございました。
これから先、会社の顧問先様・友達・親戚などからお墓の話しが出た際には、太鼓判を押して自信を持ってお勧めできる「まつしまメモリーランド」です。
これからも御社の益々のご発展と更なる飛躍を心よりお祈り申し上げます。
それから八木社長様、山形においでの際はご連絡頂ければ幸いです。お邪魔でなければまた遊びにお伺いしたいと思います。子供たちも大喜びです。
長くなりすみません。いつかこの感謝の気持ちをお伝えしたいと思っていたものですから・・・。それでは寒くなりましたので体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。(社長の健康なくしては成り立たぬ会社と顧客と社員とその家族の為に・・・)
平成19年11月21日
山形市 大谷 利加子
山形に出店することに決めてから、みんなが聞いてきた第2番目の質問です。
「山形の墓石の市場はどうなの?」
そう聞きながら、たいていは次のような事を教えて(?)くれる業界関係者も何人か居ました。
「山形は閉鎖的だよ。」
「新規の商売を始めても難しい商圏じゃないか。」
「墓石の形も伝統的で、和型一辺倒、色も黒しか使わない市場だよ。」
等々、山形に出ることにどちらかというと反対を表明する意見の方が圧倒的でした。
そんな中での山形店オープンでした。
結局オープンしてからのお客様のご要望を伺うと、なんと和型と洋型のお気に入りのデザイン割合は、仙台の店の場合とほぼ同じで、和型を好むお客様ももちろんいらっしゃるのと同じ位、洋型をお好みにあげるお客様が山形にも同じようにいらっしゃいました。
石の色もまだ若干仙台市場よりは抑え気味でも、黒オンリーでなく、グレーや白や薄いピンクや、茶系統もご契約頂きました。
やはり、山形が特別に閉鎖的守旧的な市場であったわけでなく、われわれのような会社に足を運んでいただけるのは、今までこのような提案をする石屋さんが無かったからではないかと今は確信しています。
また、お店に対する信頼感は、昔から在ったからとか、近くに在るからとかで作られるものでなく、人と人のつながりの中から育っていくものと思います。
だからこそ、地元山形に出店しより一層地域に根ざしたお店づくりをしていけば、お客様から信頼され、皆様にお応えできる経営が出来るようになると信じています。
そんな中、山形店のオープン当初のお客様から、心のこもったうれしいお手紙を頂きました。
お客様のお許しを得て、原文のままご紹介させてもらいます。
本当に有り難くて読んでいてジーンと心に染みわたり目頭が熱くなりました。
私一人ではもったいなくて、コピーをして全社員に読んでもらいました。社員からも自分たちの仕事の意義を改めて見つめ直し、生きがいを見出したと大好評でした。
大谷様 本当にありがとうございます。
それでは、次のコラムに全文を掲載させていただきます。
先ごろ祝日で本社は休みでしたが、高校・中学校の理科(地学)の先生方より依頼があり、工場の一部と原石置き場、本社事務所を開けて地学団体研究会仙台支部の方々に開放いたしました。
こちらの団体は、県内の小中高の先生方を中心に、一般の方々へ自然科学の普及を目的にした非営利の団体だそうです。
年に数回、一般の市民の方々にも参加を呼びかけ、地学ハイキングとして、地層の見学や化石の収集等を行っているようです。
実はこの団体の先生方とはかなり以前からお付き合いがあり、今までに3 4回、当社を開放して世界の石のサンプル採集や講演会をやってきました。
今回数年ぶりに幹事の先生からご連絡があり、「休みの日なので申し訳ないが・・・」との事でしたが、こちらとしましても、『石』の好きな方々になら、商売に関係なく、是非とも『石』の魅力を知って頂きたい、『石』の文化を広める効果があればと、喜んで引き受けさせていただきました。
予想ではそんなに集まらないだろうからと、当日建築関係の部門から私を含め3名の社員に休日出勤してもらい対応いたしましたが、集合時間の9時30分になったら、来るわ来るわ、3Fに用意した椅子は全く足りなく、床に座っていただいたり立ち見の方も出る大賑わいでした。
小学校高学年から、中高生、先生方、一般の地学好きの方とおよそ80 90人の参加だったようです。
「建築で使用される世界の石材について」というテーマで約1時間私からも講演をさせて頂きましたが、いい気になって話していたら、後から聞きますと、中には東北大学の地学関係の名誉教授やら高校の岩石の専門の先生やらいらして、自分の浅い知識でお話ししたことに軽い後悔を感じたりしました。
それでも、中学校か高校の先生から、とても参考になりましたよ、実際に授業する時のヒントになりました、と言って頂いて少しは助かりました。
その後、第二工場、ストックヤードに向かい、4億年前の化石(アンモナイトや直角貝)の入ったモロッコ産の大理石の大きい板を見てもらったり、実際に端材のサンプル採集で、参加の皆さんの生き生きしたお顔を拝見し、とても良かったなと思っています。
大げさな言い方かもしれませんが、私たちの会社の社会的使命の一つに「石材の良さを広めていく」事や、墓石部門で言えば「お墓参りの習慣を後代に伝えていく」等も有ると思います。
一般の方むけにこのような機会があれば、また是非ともやらせていただければと思っています。
そろそろ前々回の宿題の答えを出さないといけないかと思います。
確認のために再度皆さんからの質問を書いておきます。
質問1・「なぜ山形市なの?」
質問2・「山形の墓石市場はどうなの?」
それに対する私の考えを述べていきましょう。
「なぜ山形市なの?」
前々回コラムでも触れましたが、今まで仙台圏を中心に既存6店舗体制でやっておりましたが、次の店舗を何処にするかは大きな経営課題でした。
事業部の各責任者に次の候補地を聞き出したところ、
A案:仙台から東方面の候補地・・・石巻市
B案:仙台から北方面の候補地・・・大崎市(旧古川市)
C案:仙台から南方面の候補地・・・白石市、角田市
当然ながら当初案では上記の三案、宮城県内の主要都市を選ぶのが最も主流を占めていました。
正直私もその三案のどれかから選ぶのが順当であろうとは思いつつも、もう一つピンと来ない、乗り気にならない、という事がしばらく続きました。
ある時、何気なく日本地図を見ていると、宮城県地図だけを見ているときと違って、仙台から真西にも大きな都市が在る事に気づいたのです。(自分の気持ちとしてはコロンブスの新大陸発見くらいの感動でした)
D案:仙台から西方面の候補地・・・山形市
D案が浮上してから俄然見方が変わりました。
その西方面には山形市だけでなく、天童市・東根市・寒河江市・上山市・中山町・山辺町・・・と周辺の市町村もあります。
しかもA案からC案でも移動時間は1時間ほどかかりますが、県外であるD案でも同じく1時間ほどの距離です。
大きな意味での仙台経済圏を考えたら、これほど大きなマーケットはない、これぞ次の最適地。
「GO to The West」
そんな思いが先行し、実は次の二つ目の質問の答えを深く考えずに、取り組んだのがプロジェクト前半の時期でした。
後は毎度の事で、都市の成り立ちや店舗立地の最適場所の検討、担当人材の張付け、そしてタイミング。つまりは地・人・天、地の利と人の和と天の時を計ってのプロジェクト進行でした。
次は大事な第2の質問への答えですが、長くなってきましたので、その答えに関しては次回に持っていきたいと思います。
実はこの山形店開設準備の期間、プロジェクトメンバーが夜を徹して山形店のオープン準備をしている間に、私は少しだけ時間をもらって、8月下旬再々度のろうすくーる講師をしてきました。
一昨年のオープンスクール+パネルディスカッションで参加させてもらってから、昨年の講師そして今年度の講師と3回目のお付き合いです。
この老人(ろう)学校と法律(LAW)学校をあわせたような「遊老学校 宮城ろうすくーる」はNPO法人 エールが主催しています。
ここの校長先生 谷 さんとの関係で今回も講師となったのですが、今回は谷校長の要望で、講演主題を頂きまして、
「墓・埋葬・戒名を自分の希望で・・・」
という結構難儀な講座名・講座内容の希望でした。
確かに葬儀も、戒名も自分のやりたいように・・・、またお墓も埋葬も自分の自由で・・・というのは誰もが望み、誰もが考えることではありますが、本当にそれが可能なのか、また本人と家族、本人と社会、或いは慣習、法律はどうなっているのだろうか・・・そんな切り口から講演の内容を組み立ててみました。
資料として活用したのが「葬儀に関わる調査報告書」や「お寺の経済学」「お墓を上手に選ぶ知恵」といったものですが、ポイントは統計や一般論でなく、如何にして皆さん各個人が自分の身になって考えもらえるか?と言う事に注力しました。
資料には数値を記入せず、自分なら何処に○をつけるか、自分の考えは標準的なのか、変わっているのか等、みんなで考えながら進める楽しい講演を目指しました。
結果としては、生徒さん(大先輩ですが)達だけでなく、スタッフの方々も興味を引いたようで、あっという間に講演が終了しました。少し早く始めたのに若干時間を延長してしまいました。
その会場には、山形店準備から直行した事もあり、1時間の講演が終わったら直ぐにお暇しようと思っていたのですが、その後も質問が相次ぎ更に30分ほどの時間オーバーになってしまいました。
うまく私の意図するところが伝わってくれたかどうかは分かりませんが、改めてそんな事を考える機会をいただいたことに感謝いたします。
その時の資料を数字を入れて添付しておきました。
この資料は意外と面白いので、当社の来月の営業会議(10/1)で取り上げるつもりです。
ご興味のある方は、当社各店の営業担当者に言っていただければ、資料として分かるようにさせておきたいと思います。
当社の営業がどれだけきちんと会議を聞いているか確認の為にも、是非とも皆さんから質問してやってください。
きっといい刺激になると思いますので。
山形店出店の続きの話しは次回にさせていただきました。
2007年9月1日(土)に宮城県外で始めての店舗、「まつしまメモリーランド山形店」をオープンしました。
オープンセレモニーの挨拶でも述べさせて頂きましたが、今回の山形店出店に関しては会社の中からも、外からも、出会う人皆さんから次の2つの質問を言われました。
「なぜ山形市なの?」
「山形の墓石の市場はどうなの?」
その答えを述べる前に、出店の経緯を話したいと思います。
漠然と県外出店を考え始めたのは昨年からで、キッカケは多賀城店のオープンでした。
昨年11月多賀城に出店すると多賀城市・塩釜市・七ヶ浜町・利府町など新しい地域のお客様が大幅に増えましたが、逆に泉店や長町南店などの既存店では、それまで行かれていた多賀城近辺のお客様が当然のごとく減少すると思いきや、それ程変わらず以前のようにご来店されました。
意外に感じたのはお客様は思ったより広域的に動き、地元だけで買い物してるわけでなく、墓石などの特殊なものでも、良い店・良いサービスを求め広く県内全域を見て歩かれているということでした。
泉店には遠く県北や気仙沼方面からもお客様はいらっしゃいますし、長町南店には、白石市や大河原町の県南地区から、北松島店は石巻市や女川町などの沿岸地域からもお客様がご来店されます。
お客様の利便性や地域性を考えて、これまでの出店を計画してきましたが、きちんとしたお店づくりで信頼に応えられる店舗であれば、お客様は遠くからでもいらしてくれる、現状の県内6店舗体制でもかなりのエリアをカバーできるのではないだろうか?それならそのエリアを超える本当に遠い所に出店すべきか?どの位離れればいいのか?等の課題を持ちしばらく様子を見ておりました。
山形プロジェクトとして本格的に動き出したのは今年の春からです。
ここに至るまでには、本当にいつも思うことながら、その場その場での多くの人との出会いに助けられました。
いろんな事が都度出てきましたが、9月1日午前8時45分、御来賓の方々にお祝いをして頂きオープンいたしました。
あらためてここまで来れた事に感謝です。
ありがとうございました。
残念ながら今回は経緯だけで終わってしまいましたので、冒頭の2つの質問への答えは次回コラムで触れたいと思います。
イタリア石材業会にも何度と無く好不調の波は有ったでしょうが、近年の中国石材業界の台頭は、もっとも深刻な影響を及ぼしていたと思われます。
イタリアの石材産業の強さをこの中国との関係において少し述べていきたいと思います。
今からおよそ10年ほど前(1997年頃)、それまでみかげ石の世界市場を制していたイタリア石材業界にとって、中国のみかげ石の進出はアジア市場を奪われただけでなく、足元のヨーロッパ市場でも競合となる強力なライバル出現でした。
その当時あるイタリア人が、得意先のドイツの業者からの依頼で、中国石屋との見積もり競争をしました。当然ながらドイツの工事現場渡しの価格を提出してきた中国価格が、イタリアの工場原価にもならない、運賃は全く見ていないのか? 中国は重い石を魔法のじゅうたんか何かでただで運べるのかと、半ば真顔で聞いてきたりしていました。
それ程に価格の差の衝撃は大きく、イタリアにとって厳しい時代の始まりだったと思います。
それから5年ほど経って、イタリア国内でみかげ石しか取り扱っていなかった石材業者は、一部は倒産し、一部は縮小せざるを得なく、ほんの一部だけは逆に中国から安いみかげ石を輸入しヨーロッパに卸したりして食いつないだものの、その多くは企業存続に大きな変化を引き起こした憎い仇でした。
それからさらに5年ほど過ぎて、現在はどうでしょうか?
なんとその巨大な中国の石材業界を逆に得意先にしてしまいました。
中国は「大理石」の名称が中国雲南省大理から採れたことによる命名である事からもわかるように、たくさんの大理石が産出されていますが、管理の仕方や丁場の状況や運搬方法など多くの点でイタリアの大理石に大きく遅れをとっています。
そこに目をつけてイタリアの大理石業界が中国に大量に大理石の原石を供給しだしたのです。おそらくイタリアで採れる大理石原石の70% 80%は中国向けでしょう。(大理石製品や半製品はほとんど中国向けは無いが・・・)
それに関して面白い話があります。
イタリアの石の産地で東洋人を見ると
20年ほど前は「ジャポネ?」
15年ほど前から「コリア?(韓国人?)」
最近は「チネーゼ?(中国人?)」
と最初に聞かれます。
多くの検品員が滞在してますが、本当に最近は日本人と会うことが極めて少なくなりました。
さらにはまた、イタリアのみかげの会社も最近復活の兆しを見せています。
理由は、中国が輸出するのに不得意な所、地の利の無い所で積極的に販売網を広げている為です。
具体的にはロシアやウクライナ、ベラルーシの旧ソ連の国々、南米ボリビアやパラグアイ等中国の影響のほとんど無い所は、イタリアの独占市場です。
それからやはり、石の使い方のバリエーションの多さも、イタリアの強みでしょう。
石のマーケットの拡大と共に、素材の使い方、利用方法などやはりイタリアには歴史と強さを感じます。
写真1はお墓への使用です。「フィレンツェの教会内のミケランジェロのお墓」
写真2は家庭での使用です。「友人のマリオの家の台所、流しとキッチンカウンターが石です。」
写真3は広場での使用です。「ピエトラサンタの広場に建つ日本人彫刻家安田侃氏の大理石彫刻」
この3つは全て同じ産地の同じ石から出来ています。
今回は先月末(6月23日 29日)イタリアのCARRARA地区出張の件について書いていきます。
以前は最低でも1年に1度はイタリア、スペイン、ポルトガル等ヨーロッパの主要大理石産出国を訪れ、大理石の状況調査や商談・検品を行っていました。
ここ2,3年は輸入スタッフに代理で行って貰ったり、また国内建築需要の縮小やヨーロッパ通貨ユーロの高騰で控えてもいました。
今回は2004年6月以来3年ぶりの訪問でした。
CARRARAはトスカーナ州地中海沿岸にあり、斜塔で有名なPISAから30分程、観光地で有名なFIRENZEから約1時間ほどの、白い大理石を産出する石の街です。
そこではあのミケランジェロが彫刻用に掘り出した大理石の坑道も残されており、また古代ローマ時代のキリストが生まれる遥か昔からの石産業の歴史が続いているところです。日本の石屋のせいぜい100年、200年の歴史からすれば、桁が一つ違う1,000年、2,000年の知恵と伝統があります。
その数千年の間、そこから切り出された白い大理石は、その時代々々のもっとも豊かで、力があって、勢いのある国々の建造物の素材となって輸出され続けました。
古くはローマ・ペルシャ・フランク王国を始め、近代ではイギリス・フランス・スペイン・オランダに輸出し、近年ではアメリカや香港、日本もその主要な販売先でした。
1990年前後日本でバブルと呼ばれた頃には、イタリア人の目はアメリカを抜いて確かに日本に向けられていました。
高級な大理石を大量に購入し、当時の円とイタリアリラの通貨の強さの違いもあり、このエリアにも現地検品員として日本人がたくさん居た時代でした。
その後、アメリカの建築が一段落し、日本は最悪の不況下に陥り当時の主要販売先がみんな駄目になる中、イタリアの石屋さん達は、見事に乗り越えて活況を呈しています。
それこそが数千年の歴史の知恵と伝統なのだろうと思います。
その事は、次回で詳しく述べていきましょう。
写真 は、ここCARRARA地区で産出される石の一つ、アラベスカートコルキアの検品写真。
写真 は、珍しい化石(長いのは直角貝、丸いのはアンモナイト)の大理石です。約2億年前のものです。
カウンタートップや飾り壁、床材などに使えます。ご要望があれば各担当窓口店へお申し付け下さい。
今回は当社のテレビCMの事について書いていきたいと思います。
2007年現在、テレビで放映されているのは五作目のCMバージョンです。
一作目は1号店の泉店オープン時代、ご夫婦が広瀬川の河畔に向かい、夕日に照らされながら静かに微笑み合う、心落ち着く仕上がりのCMでした。
引き続き2号店オープン後は、そのご夫婦のモデル(役)と息子夫婦(役)に2人の孫(役)の6人が公園でブランコ遊びをし、リビングでくつろぐアットホームな出来映えが二作目です。
三作目は確か3号店の開店前後のバージョンだったと思います。
CMソングを全面的に打ち出し、歌のお姉さんと一緒に子供たちがメモリーランドの歌をうたい、公園の中シャボン玉で遊ぶシーンが印象的でした。
四作目は中山店オープン後です。
「ショールームという新しさ」
「墓石にもショールームスタイル」
「雨や風でも快適な展示場」
このような当社のコンセプトを打ち出すために、傘をさしたご夫婦が雨に打たれ雪に降られて来られても、ショールームに入った瞬間傘が消えて快適な室内が現れる。
この時のモデルさんは東京から来られた方でした。
今回六店舗になりCMの改変が必要になって考えたのは、大げさな言い方かもしれませんが、地域還元とか社会的使命(本当に大げさ過ぎて申し訳ありません)という言葉が頭の隅にありました。
今までは全てプロのモデルさんやタレント事務所の方に出演してもらっていました。
三作目の子供たちも子役事務所で歌唱力テストまでして選ばせて頂いたセミプロの子供たちです。
これを一般の子供さん方に開放してテレビに映る機会をあげたらどうだろうか、喜んで出てもらえないだろうか、別にモデルじゃなくても本当に普通の子達がテレビで歌ったらどうなんだろうか・・・
それからもう一つ、お墓参りや手を合わせるという習慣を、途切れる事無く次の世代に伝えていく、これは家庭だけでなく社会やわれわれ石屋も重要な責務を背負っている、そんな想いもあって、一般の子役キャラクター募集ということになりました。
小さな記事での募集でしたが、すさまじいばかりの反応で、10倍以上の応募があり、どの子たちも本当に甲乙つけ難かったのですが、六店舗をイメージして制作会社のほうで6人だけ選ばせていただきました。
今回選に漏れた方々には本当に申し訳なく思っています。
多くの人に機会を渡したいと思います。次回も企画しますのでこれに懲りずに応募してください。
そして出来たのが、現在の五作目の「墓石は心のふるさと」編です。
当ホームページのメディアギャリーに公開しております。
(合わせて三作目、四作目も公開中です。)
写真はオーディションの一コマです。
第1回のCAD立体図をご提案したところ、お母様からは
「まわりはシンプルに」「お掃除がしやすいように」
「屋根はもう少し厚く」「なだらかな曲線で」
「本体は少し明るく」「もうちょっと豪華に」・・・
と何回かのお打ち合わせでご本人のイメージもだんだんはっきりとしてきて、かなり具体的な図面を作ることができました。
しかしながら、その図面を見てまず驚いたのが屋根石の大きさです。
約2.5メートル×2.5メートル、厚みは40センチメートル。このままだと7トンもの重さです。
もちろん四角の石から上の分を削ったり、六角形に切ったりするので半分以下にはなるものの、それでも3 4トンの石が空中に浮く格好になります。
当社の墓石は、耐震工法で地震が来ても安心な施工を行っていますが、さすがに空中にそれだけのものを、そして安心して御参りできるようにするには、単純な工法ではだめだと改めてご依頼の難しさに頭を抱えてしまいました。
さらには、原石の採掘場でも(丁場と言います)、そんな巨大な石はほとんど出てこないし、また仮に採れたとしても、丁場から工場へ運べない、加工できない、コンテナに載せられない、無理にやっても費用が膨大になる・・・等々各担当者からダメだしをもらってしまいました。
「無理だよ」と親友を通じてお母さんに言ってしまおうかと何度も思いましたが、亡くなったお父さんの姿が目に浮かび、やれるところまで、可能な形でご提案しなおそうと各部門の調整をかけました。
幸い当社には、建築工事部があり、工事部の本部長も巻き込んで、重量物を支える強度計算、基礎・地中梁の構造計算、石と金属のダブル構造の柱・・・結局、耐震施工は全面的にビル建築の手法で可能である事を見出しました。
また、丁場は当社のアモイ事務所から、丁場オーナーに特別大きな原石を譲ってもらう約束をし、また中国の工場の社長には特殊な加工機と、それ以外は手加工でやってもらう話を取り付けました。
最後は海上を運ぶコンテナの大きさです。これはどうしても箱の大きさが決まっていて、また梱包して取り出す関係で船会社にも確認し、この条件下で積める最大の大きさ
「2,350×2,150×400、重量約2.8トン」
これならやれると言う確信を持って、再度設計し、ご提案という形になりました。
それでも念のため先に親友に来てもらい、本当に屋根付きで考えているか、お母さんには普通のお墓に戻してもらうよう説得しようか、と事前に相談し合ったものの、やはりお母様はお父さんと二人で話した思いが強く、親友も「母の思うように作ってやってくれ」との結論で、ご提案の通りで決定しました。
早速、当社工事部も含めた特別プロジェクトを開始し、また私も中国の工場に出向き始めて見る大きな原石を確認(写真1)、当社の総力を挙げた施工を完了し、お引渡しでお母様に満足いただいた当社自慢の屋根付きお墓が(写真2)です。
担当した社員、そして今回のプロジェクトに参加した全ての関係者が、お母様の想いを実現するお手伝いが出来たことに、心より感謝しています。
そしてその想いがまっすぐでとても強い事に、心が洗われるような清々しさを感じるのは、親友のご両親だからというだけでは無いと思います。
雨のあたらない屋根の下で永遠の眠りにつくお父様のご冥福をお祈りいたします。
Copyright © 2015 matsushima memory land. All Rights Reserved.